[ポイント1]
代謝が低下する高齢者に一般の成人と同量の処方では過剰投与の可能性あり。高齢者は複数の疾患を持ち、薬の種類も多くなりがち。
[ポイント2]
日本人の医者好き、薬好きに加え、国民皆保険で医療にアクセスしやすい。患者の飲み忘れや勝手な服用中止で残薬が膨らむことも。
[ポイント3]
カギは薬剤師。在宅患者に訪問してから医師にフィードバックすれば、あつれきが生じない形で処方薬を減らすことができるはず。

特集「納得のいく死に方 医者との付き合い方」の他の記事を読む
「5合飲めば多くの人が酔うので、酒は5合飲むこと。3合では酔わない人がいるのでダメ」
これは代表的な認知症薬、ドネペジル(代表的な薬はエーザイのアリセプト)に増量規定がある理由を説明する例え話である。開発時に1日5mgで効くことはわかった。が、3mgでは有意差が出なかった。2週間は薬に慣れるため3mgだが、それ以降は5mgになる。ほかの認知症薬にも増量規定がある。

ところが、認知症を多く発症する高齢者は脳細胞が減少することもあり、規定量以下でも効く人は効く。つまりは酒量と同様、薬も個人個人で適量が違うのだ。

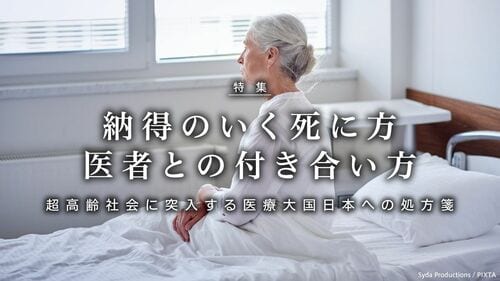































無料会員登録はこちら
ログインはこちら