おカネを求めセックスワークに向かう女性たちの現実に、異色の経歴を持つ文筆家が迫った。

深夜の新宿・歌舞伎町の喫茶店「カフェアヤ」の1階でコーヒーを買って地下の喫煙席に座ると、両脇にはたいてい風俗嬢っぽい女の子や休憩中のスカウトマン、おそらく企業人ではない若い男のグループなどが座っている。女の子は一人で「SHIBUYA109」かそれより安い店で買ったペラペラのコートやワンピースを着て、色だけは派手なバッグを持ち、たばこを吸いながらしきりに携帯電話をいじっている。始発を待っているのか男の連絡を待っているのか、私はいつもいろいろと想像しながら、相手にわからない程度にチラチラと見てしまう。
私もかつて彼女たちの一人だった。稼ぐ資本としての身体は確かに持っていて、それを使ってはいたものの、どことなく目の前にある稼ぐ手段を持て余して、何にもならない時間を潰す。財布には3万円程度は入っていたが、稼いだ現金はいつも手を通り過ぎるだけでいつも貧しかった。寝る時間はいくらでもあったが、なぜかいつも眠くて体調が悪かった。自分の月収がどれくらいあるのかもよくわからない。ただ来週一日も仕事をしなければ、家賃が払えなくなることだけは確かだった。


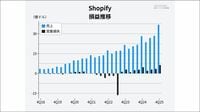

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら