さらに本書を読んでいて気付かされるのは、感染症危機対応のための制度を整えることと、それをうまく機能させることは、必ずしも同一ではないということだ。著者は感染症危機管理の組織モデルとして、アメリカのCDCにたびたび言及し、CDCが軍を模倣した細分化されたシステムであることを説明している。一方で、そのような理想的なシステムを備えたアメリカが新型コロナパンデミックで、世界最大の感染者数を出すことになったのはなぜなのだろうか、と考えさせられるのである。
またWHOに関しても、感染症危機時には、平時の組織とは切り離された参謀組織が起動すると説明されている。そのようなシステムを兼ね備えた組織が、なぜ、新型コロナ対応で世界的な非難を浴び、外部の調査パネルが立ち上げられるに至ったのだろうか。おそらく大戦略のレベルで、優れたリーダーシップを伴わなければ、制度はうまく機能するとは限らないということなのだろう。アメリカは優れた危機管理システムを備えながらも不幸にも、実際の危機が生じたとき、科学を軽視し、専門家を非難する人物が大統領だったわけだから。
何が危機管理のボトルネックだったのか
危機で味わった痛みは、不思議なことに時間と共に、忘れ去られる部分も多い。しかし、感染症はこれが最後ではない。近年、気候変動や都市化、ポピュリズムと連動した反ワクチン運動等を理由として、数々の新興・再興感染症が途上国のみならず、先進国でも頻繁に見られていることを踏まえれば尚更である。すなわち、感染症の脅威は今後も持続的に続くと考えたほうがいい。
2021年10月に就任した岸田文雄内閣総理大臣は、その所信表明演説で、「これまでの対応を徹底的に分析し、何が危機管理のボトルネックだったのかを検証します。そして、司令塔機能の強化や人流抑制、医療資源確保のための法改正、国産ワクチンや治療薬の開発など、危機管理を抜本的に強化します」と述べた。その過程においては、本書が間違いなく、参照されることだろう。同時に、制度の運営には優れたリーダーシップが伴わなければならないことも、忘れてはならないだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




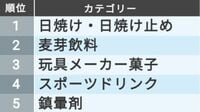




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら