――社員同士が同じ空間にいないと、業務管理上の課題はありませんか。
これも、リモートになったことでチームごとに「朝会」をやるようにしている。雑談をしたり、昨日これをしました、今日何をします、今こういうことで困っていますということを共有している。チームによっては業務終わりに「夕会」もやっている。
営業面では「Salesforce(セールスフォース)」をもともと使っているので、すべてクラウド上で管理できている。エンジニアもビジネスチャットの「Slack(スラック)」で進捗を連絡し合っている。
もともと何でも共有することが当たり前という文化があることも大きい。属人的ではいけない。全社レベルでいえば、この月、この四半期で達成したいこと、それに対する進捗を月次でスプレッドシートで共有している。
リアルオフィスへの出社は“カルチャー”次第
――リモートワークがもっと進むと、オフィスはいらないのではないですか。
業種によっては物理的に対面しないとできないこともある。マッサージのようなサービスや工事現場、工場などだ。ただ、ほとんどすべての仕事は理論的にはリモートが可能だ。
あとは文化の問題になる。チームとしての一体感を大事にするのであれば、オフィスで来て一緒にやろう、そのほうが楽しいよね、という考えもある。一方で独立性やプロフェッショナリズムの高い組織であれば、全員リモートということもありうる。業務自体はリモートで回るはずなので、「カルチャーとしてのリアル出社」という世界観が生まれるかもしれない。
また、採用面でのリモート活用もある。優秀なエンジニアだが、東京では働きたくないという人もいる。リモートを許可することで採用できる対象が広がる。
「コロナ後の世界」が語られ始めているが、BCPとしてリモートを可能にしておくことは重要だ。どんな災害にも共通している。今回は地震が起きた場合よりも影響が広範囲で、今後の働き方を変えるきっかけになっていくだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

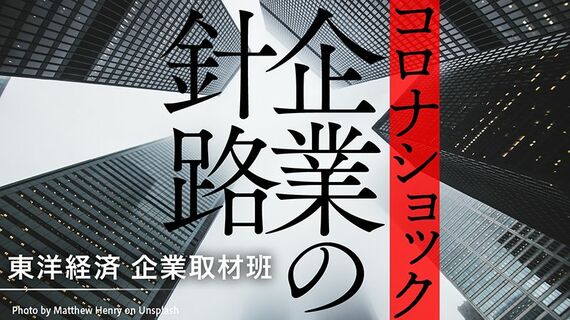






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら