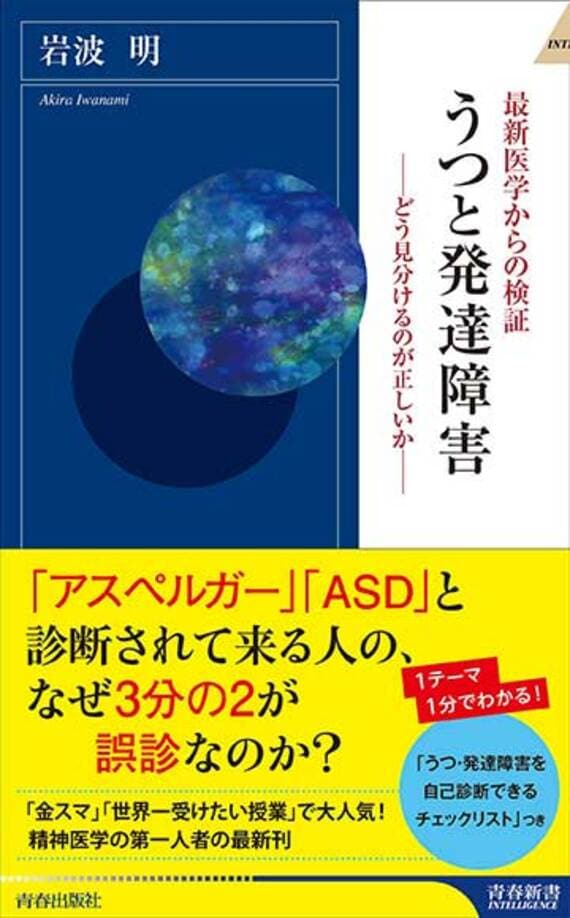ADHDに「適した職業」「適さない職業」の決定的差 マルチタスクな机仕事はオススメできない
以前、烏山病院に通院している発達障害の患者を対象に、仕事の内容を調べたことがありました。すると、ADHDの人は専門職が多く、ASD(自閉症スペクトラム障害)の人は定型的な事務職が多いという結果が出ました。
ADHDは静かなデスクワークが苦手で、マルチタスクも混乱の種になります。自分の裁量でできる仕事、例えばイラストレーター、作家、コピーライター、プログラマーなどの分野が多かったのです。
一方ASDは、決まった作業を続けることは比較的得意で、デスクワークも苦にはなりませんが、周囲に突然話しかけられたり、新しく指示をされたりすると、やはり混乱しやすいという特性を持っています。
私たちの調査の結果、ADHD145例のうち、専門的・技術的職業が48%、事務従事者34%、サービス業6%、運輸・包装・清掃6%という内訳でした。またASD348例のうち、事務従事者が54%、専門的・技術的職業26%、運輸・包装・清掃8%、サービス業5%でした。
ADHDの人は、話し方も、普通の人より早口で、落ち着きなく過剰さを感じさせることが多いと思います。
会話で「ズレた回答をする」理由
さらにいうと、話の要点がズレることも、よくあります。ADHD当事者は、相手のほんの一言に反応して、思いついたことを一方的に話し続けてしまいがちだからです。
休職していたADHDの患者が「就職説明会に行ってきた」と言うので、「何社ぐらいの説明を受けましたか?」と尋ねました。彼は、こちらの質問には答えず「自分はこういう仕事をしたいから就職説明会に行ったんだ」という話を延々と続けました。
彼は、自分の考えを伝えたいという衝動を抑えられなかったのです。話の合間で、もう一度、同じ質問をすると、彼はやっと「1社だけです」と教えてくれました。
このようにADHDの人には、話の要点を捉えずに、自分の関心に従って、たった一言に強く反応してしまうという傾向がみられます。そのために、相手が何を聞こうとしているか理解しようとしないで、話がズレてしまいがちになるのです。本人は、その点に自覚がないことも多く、話もどんどん長くなるのです。
けれどもこうした会話は、職場など社会生活においては大きなマイナスです。相手の話をきちんと聞き、それに対して話を進める工夫は重要です。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら