「PDCA・コスパ・KPI」が第4次産業革命を潰す理由 数学が国富の源泉になる「数理資本主義」時代
これらを見る限り、わが国は、「数理資本主義」において優位を確保できるだけの若い才能に恵まれているように思われる。
時代遅れの「数学は役に立たない」という先入観
問題は、その若い数学の才能を、デジタル技術のイノベーションに活かしきれているのかどうかだ。
例えば、国際数学オリンピックの予選通過者は医学系へ進む者が多いという調査がある。おそらく、収入や雇用がより安定した職種として、医者が選ばれているのであろう。
裏を返せば、大学の数学研究や企業のデジタル技術開発部門が、若い数学の才能を引きつけるのに十分な雇用環境を提供していないということだ。
また、日米の数学の博士課程修了者を比較してみると、アメリカの博士課程修了者の数は、日本の10倍以上である。しかも、アメリカでは産業界へ進む者の割合はおよそ30%であるが、日本は10%程度である。
また、「Nature Index 2017 Japan」によると、2005年から2015年の日本の論文出版数は、14分野中11の分野で絶対数が減少しており、しかも減少率が最も大きかったのが計算機科学(37.7%)であった。数学分野では、論文数は増加しているものの、その伸びは世界に比べて鈍化しており、物理学分野にいたっては減少している。
理論研究がデジタル技術の革新に直結する「数理資本主義」の到来を前にして、肝心の数学・物理学を含むわが国の研究の力が弱ってきているのだ。
その原因は、高等教育機関への人口当たり公的研究資金の伸びが過去20年間、停滞し続けたことや、若手研究者の雇用が不安定化したことである。平成の大学改革の失敗や財政健全化という過誤が、こうした事態を招いたのである。
大学だけではなく、企業側にも問題があるかもしれない。日本では、技術開発の中核となる人材はもっぱら「工学」出身であった。そのためか、「数学は役に立たない」という時代遅れの先入観がいまだ残っているのかもしれない。
また、高度な数学は、極めて抽象度が高いために、数学研究の具体的な成果をあらかじめ想定しにくい場合が多い。昨今は、企業でも政府でも、短期的な視野で、性急に具体的な成果を求める風潮が強いが、そんなことでは、金の卵を産む鶏と言うべき数学の才能を殺してしまう。
数学者は、数学が何かの役に立つからとか、高い地位や収入が得られるからといった理由で、数学を研究するのではない。単に、数学が面白いから、数学が好きだから、研究するのだ。
そういった強烈な知的好奇心や興味が動機となって、優れた数学研究が生み出され、それが結果としてデジタル技術のイノベーションへとつながる。
したがって、「数理資本主義」の時代には、KPIを設定したり、PDCAサイクルを回したり、費用対効果を厳格に評価したりするような企業経営や経済政策は、かえってイノベーションの芽を潰してしまう。そうではなくて、数学者の個人的興味や知的好奇心を最大限に尊重し、自由に活動させるような、これまでとは違ったマネジメントが求められるのだ。
そのようなマネジメントを編み出した企業や国こそが、数理資本主義の時代の勝者となるであろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら















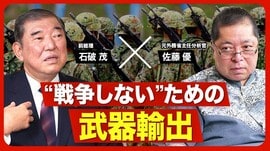















無料会員登録はこちら
ログインはこちら