保育園業界を蝕む「助成金不正受給」の実態 企業主導型保育の穴狙い、助成金ビジネスか
A社の担当者は、「旧園を廃止して園児を移せ、とは言っていない」としながらも、「(担当者がB園に対して)営業をした2016年8月時点で、看板の掛け替えが助成金の対象にならないとは知らされておらず、(新B園が開園した後の)11月ごろ急に決まった」とも主張している。
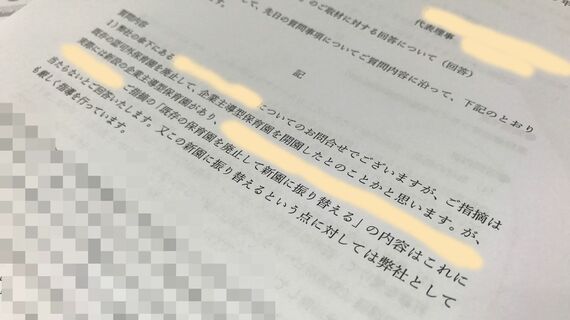
結論としてA社は看板の掛け替えにより不正に助成金を受給していることを否定したが、その発言には以上のように矛盾も多い。
新旧施設、監査の管轄が異なり「並存」見抜けず
既存の保育園からの看板の掛け替えであることを、助成を決定する段階で見抜けない制度にも問題がある。その原因は、認可外保育と企業主導型保育の管轄が異なることにある。新施設の助成決定や、その後の監査などを担うのは、企業主導型保育の助成を担当する内閣府の外郭団体、「児童育成協会」。一方、旧施設の認可外保育施設の立入調査を担当するのは、園が所在する自治体だ。自治体が関与しないことにより企業が柔軟に取り組めることが企業主導型保育のメリットだが、今回はそれが裏目に出たかたちだ。
A社がある自治体の場合、認可外保育施設の立入調査は毎年行われており、各施設から自治体に労働者名簿を提出することになっている。したがって、旧施設と新施設の名簿を付き合わせれば、保育士などの従業員が二重に登録されていることが発覚するかもしれない。
ただ、児童育成協会によると「一般論として、自治体から情報提供を求めるようなことはない」(担当者)。自治体側も、「園児や従業員が移っているのかどうかを確かめる手段はない」という。この縦割りの弊害によって、A社のパラレル経営は発覚を免れていたのではないだろうか。
児童育成協会の担当者は、「既存の園からの看板の掛け替えがNGであることは従前から繰り返し周知しており、11月になって急に決まったという事実はない。一概には言えないが、一般論として看板の掛け替えであると判断できれば、助成金の取り消しもあり得る。放置することなくリスク管理はしっかりやる」と述べる。
企業主導型保育事業は、あくまで待機児童を減らし、育児と仕事の両立を促進することを目的としており、企業からの拠出金を原資とした多額の助成金で運営されている。こうして制度の穴を狙った事業者が得をする現状には、疑問を呈せざるをえない。
なお、本記事では、当該企業を実名ではなく、A社と記してきた。A社は補助金を不正に受け取っている可能性が濃厚である。ただ、保育園運営業者の補助金・助成金の不正受給はA社に限らず複数行われている疑いがあり、1社固有の問題ではない。また、待機児童問題解消のために保育園増設が急がれる中、行政側の管理が甘くなっていることこそが問題の本質である。
以上の理由から、1社固有の問題に矮小化されることがないよう、あえて実名を伏せた。該当する保育園運営会社には、これを機会にぜひ改めてほしい。また、今後の行政側の動きにも期待したい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら