私の友人で、スタンフォード大のMBAを修了した中国人がいますが、国有企業に入るべく、3カ月間就職活動を頑張っても、ことごとく不採用になり、結局、外資系の金融に落ち着きました。
MIT(マサチューセッツ工科大学)スローンMBAを修了した知人によると、同MBAを取った大陸出身の人は全員外資系の企業に入ったのですが、それは本意ではないそうです。多くの留学生は経済成長の著しい祖国に帰って働きたいと思っています。しかし、大陸で魅力的なオプションのひとつである国有企業に入ろうとしても、共産党員でもなく、国有企業のしきたりや文化、コミュニケーションルールにもついていけない自分が入ったら、たぶんうまくやっていけない。日本の大企業に中途で入ったように浮いてしまって、キャリアパスを描けない。それで、仕方なく香港で外資系の金融に入る人が多いようです。
外資系から国有企業への転職も難しいようです。私と昔一緒に働いたことがあるマッキンゼーの中国オフィスの知人をみても、マッキンゼー出身者で「体制内」に転職できた人は、ほとんどいません。中国のトップ大学である北京大学を優秀な成績で卒業しても、いったん外資系に入ってしまうと、その後、「体制内」になかなか入れない。
つまり、帰国子女や外資系企業出身者にとって、「体制内」の壁は万里の長城のように厚く高いのです。
政府が民営企業にイチャモン
ところが、最初に「体制内」に入ってしまえば、内部では人材の流動性が非常に高い。中央官庁から国有企業へ、また国有企業から中央官庁や競合の国有企業への転勤はごく普通にあります。それは、国資委(国務院国有資産監督管理委員会、中国の国有企業を管理・監督する組織)がすべての国有企業を管理しているからです。イメージとしては、ひとつのホールディングカンパニーが150社ぐらいの国有企業を統括している状態です。日本でいえば、NTTの社員をソフトバンクに異動させて、その後、国土交通省に異動させる、みたいなことは日常茶飯事です。
中央官庁の高官が国有企業の社長になったり、国有企業の社長が中央官庁の高官になったりもします。日本の場合、中央官庁から民間企業に天下りするのは、年を取ってからですが、中国は若くても公務員から国有企業への異動がひとつのキャリアパスとして存在します。政策を作って、企業でトップもやって、また政策を作る。仕事が国の政策と結び付いているので、面白く、やりがいもあるでしょう。
「体制内」で人材がくるくる回り、「体制外」でも中国は転職や起業が多いですから、人材の流動性が非常に高くなっています。しかし、「体制内」と「体制外」の間を行き来している人はほとんどいません。最初のピットレーンで2つに分かれたら、その後で交ざることはないのです。帰国子女は片道切符で「体制外」に行ったきり、戻って来られません。
また、最近「国進民退」という熟語がよく聞かれるようになりました。この5年間、体制内の力がどんどん増して、民間企業をはじめとする体制外の力が衰退してしまったという意味です。
そもそも、国有企業は事業展開上、その権限を最大限に利用しています。われわれのようなスタートアップ企業は銀行から融資がもらえたとしても年利率は20%で、大型の民営企業でも10%です。ところが国有企業だと、平均5.3%で融資を受けていると言います。薄熙来が市長として権力を振るっていた重慶をはじめとして、政府が民営企業にイチャモンをつけ不当に利益を得ることさえよく起こっています。



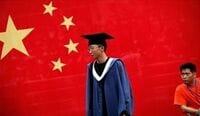



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら