"理系ママ"、少女の心で世界に挑む 新世代リーダー 上川内あづさ 名古屋大学大学院教授
ドイツ留学が人生の転機
それから6年間、大学院の博士課程まで同じ研究室でミツバチの研究に打ち込み、見事、博士号を取得。一人前の研究者になったというお墨付きを得た。このときにはもう、研究を続けていこうという思いは固まっていた。

「大学院修士課程の2年生くらいで、研究者として一生やるかどうかはまだわからないけれど、博士号を取ってから少なくともしばらくは続けたいと思いました。
当時はポスドク(博士研究員)一万人計画の時代で大学に資金が付いていたので、ポスドクの口はいっぱいありました。その先のことまでは考えておらず、進路に葛藤はなかったですね。私たちのころは、皆夢を持って研究者になっていきました」
ポスドク時代は、当時愛知・岡崎市の基礎生物研究所にいた伊藤啓氏の研究グループで過ごす。この時、研究対象をミツバチからショウジョウバエに変えた。ショウジョウバエの方が、脳の神経回路を研究する手法がたくさん確立されていたからだ。
新婚から一転、異国での別居生活へ
そんな上川内さんに、ドイツ留学のチャンスが訪れる。
「シカゴの学会で研究成果をまとめたポスターを展示して説明しているときに、たまたま隣で発表していたドイツの研究者が、『興味も似ているし、面白そうだからぜひ一緒にやろう』と誘ってくれました。運命的かというと、ハエの聴覚系をやっている人はそんなにいないので、学会で隣になったのも、当然といえば当然ですね」
ドイツ留学は、私生活での節目にもなった。ドイツのケルン大学への3年間の留学生活が始まる直前、当時交際していた研究室の先輩と結婚。せっかくの新婚生活がいきなり別居で始まり、不安や寂しさはなかったのだろうか。
「今も別居ですが(笑) 寂しがっている余裕もなくて、ドイツで生活するだけで大変でした。初めての海外生活で、多少孤独感もあり、疲れましたし。ドイツ語は2カ月間だけ現地のドイツ語学校に通いましたが、ほとんどしゃべれないですね。物が買えて、相手が何を言っているかうっすらわかるくらい。
ドイツでは、早くいい結果を出そうと焦ってちょっと頑張りすぎて、入院してしまいました。お医者さんは英語が話せるのですが、受付の人や看護師さんが全然だめで、入院前の検査では2回に1回くらいしか目的の場所にたどり着けなくて、すごく大変でした」
だが、異国での努力が結実する。
帰国後、東京薬科大学の助教に着任し、ドイツ時代の研究に追加実験を加えた。その研究の論文が、世界で最も権威のあるイギリスの科学誌、『ネイチャー』に掲載され、文部科学省から若手科学者賞を受賞。研究者として一躍脚光を浴びる。

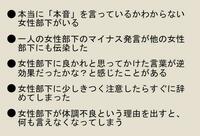

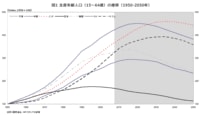



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら