ワインの近代化 その1 その背景:科学の発展《ワイン片手に経営論》第10回
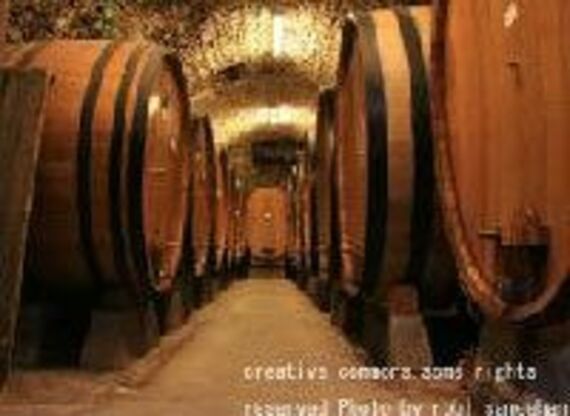
■科学の本質は「分ける」こと
科学とは、そもそも何なのでしょうか?広辞苑によると次のような定義が記されています。「観察された実験など経験的手続きによって実証された法則的・体系的知識。また、個別の専門分野に分かれた学問の総称。物理・化学・生物学などの自然科学が科学の典型であるとされるが、経済学・法学などの社会科学、心理学・言語学などの人間科学もある」。
また、新漢語林という漢和辞典で「科」を調べると次のように書かれていました。『(1)しな。品等。等級。(2)ほど。程度。きりめ。区分。(3)すじ。箇条。条目…(4)類別。区分。「文科・理科」…』。
第1回のコラムでも記しましたが、「科学」という言葉が持つ一つの本質は、「分ける」ということです。「分ける」とはモノゴトが「分かる」ということであり、そのためには「分析的視点」でモノゴトを大雑把にではなく、ひとつひとつ丁寧に見ることが必要です。
分析的視点とは、「木」を見るにあたって、根・(茎)幹・枝・葉・花、さらに花を花弁・おしべ・めしべ・がくといったように一つひとつ観察することです。これは、一つひとつの細部を「意識」することであり、その細部がどういう「メカニズム」で、どう組みあがって「全体を構成」しているのかを明らかにしようというのが、「科学」の一つのアプローチです。
ただし、このアプローチには欠点も存在し、幾ら分析的に細部を観察しても何も分からないこともあります。例えば、人間という生命の謎を解き明かすために、人間を細かく分けて、しまいには細胞、さらには遺伝子まで観察してみるのですが、なぜ人間という自律的生命が動いているのか、循環器系、骨格系、神経系、筋肉系、生殖系という系がどうして機能しているのか、実はよく分かっていません。
では、なぜ科学(≒分解)するのか。それは、17世紀のころに遡って科学の歴史を振り返ると分ってきます。
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事






























