10年で大変貌「官能都市ランキング」から考える「都市の魅力の作り方」《文京区、武蔵野市、金沢市は低迷。千代田区、中央区、豊島区が飛躍》
「ひとつは再開発に関わるインセンティブを変えること。建てることにボーナスを出すのではなく、建てた後のエリアマネジメントや小規模事業者誘致に補助を出す、毎年の税金に軽減措置を適用するなど、関わり続けることをメリットにすることが考えられます。
もうひとつはプレイヤーを見直すこと。建物竣工後も開発エリアに関わり続け、その地域の成長を促すことを開発者あるいは所有者のインセンティブにするためには住宅を分譲する開発ではなく、オフィスや商業施設、賃貸住宅を作る開発にしていく必要があります。
ただ、7大都市圏以外で大手が賃貸事業で採算を合わせるのは難しい。でも、地元のデベロッパーなどなら合う可能性は高くなる。そうした地域のプレイヤーが地元の開発に挑めるような状況が生まれれば都市圏以外の地域の魅力をアップさせられるかもしれません」(島原さん)
建物完成後も関わり続ける開発が次々に
その観点で今、島原さんが注目しているのは自由が丘駅前の再開発だという。この開発では地元の事業者が自分たちの土地を手放すことなく、再開発を行っている。
誕生する住宅も分譲ではなく賃貸。地元の事業者は今後も地域に関わり、将来にわたって地域に責任を持つと宣言しているともいえるわけで、そうした事業者がどれだけいるかが地域の今後を左右することになるのだろう。


ちなみに再開発で地権者が土地を手放さずに行われた事例としては香川県高松市の丸亀町商店街があるくらいだが、今後は自由が丘以外にも同じやり方で地域に関わり続ける事業者が増えることが予想される。
すでにJR東日本が進める広域品川圏構想の中でTAKANAWA GATEWAY CITY(以下高輪ゲートウェイシティ)、大井町駅直結複合施設「OIMACHI TRACKS」に誕生する住宅は全戸賃貸であることが発表されている。
その理由は高輪ゲートウェイシティを「100年先の心豊かなくらしのための実験場」と位置づけているからだろう。自社保有の土地で実験としてまちに関わり続けるなら、住宅を分譲、権利を分散させてコントロールできなくするのは得策ではない。
体力のある、長期に関われる事業者のまちづくりとしてはトヨタ自動車による「Toyota Woven City」(静岡県裾野市)も姿を現し始めた。JR東日本同様、もともとはまちづくりの会社ではない会社が長期的な視野のもと、モビリティを中心にした新しいまちづくりを始めるのである。
こうした建物完成後にもまちに関わり続ける開発が次々に登場、成果を上げるとなれば、従来型の開発をしてきた会社にも影響が及ぶ可能性は十分ある。
結果、売っておしまいではない開発、引きこもったままでないまちづくりを始めようとする事業者、地域が増えてくれば都心部以外も変わるかもしれないと思うが、さて、島原さん、いかがでしょう?
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



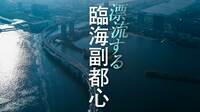



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら