10年で大変貌「官能都市ランキング」から考える「都市の魅力の作り方」《文京区、武蔵野市、金沢市は低迷。千代田区、中央区、豊島区が飛躍》
そこでレポートでは、開発でセンシュアス度の上がった都市に共通するポイントを上げている。ポイントは3点ある。ひとつは「開発を経てどのような街が作られたか」。
「東京や大阪の都心部のようにもともとオフィス街だった業務エリアに居住人口を集める住宅開発か、住宅地に働く場所や遊ぶ場所を集積させる商業開発のいずれか、つまりミクストユースが進む開発がセンシュアス度を上げています」(島原さん)
暮らすだけ、働くだけではなく、それらが同時にでき、加えて遊べる、楽しめる開発が選ばれているというのである。
逆に住宅エリアの駅前で住宅だけを供給する開発では個人経営の店舗や小規模事業者がチェーン店などに置き換わることが多く、地域の均質化が進む。会話や飲食の楽しみが減るわけで、それが官能度を下げることにつながっている。
開発そのものよりも重要と思われるのが、「開発エリア周辺での継続的なまちづくり活動の存在」だという。いわゆるエリアマネジメントである。
たとえば、レポートでは千代田区の「大丸有まちづくり協議会」(三菱地所)、「淡路エリアマネジメント」(安田不動産)、中央区の「日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会」(三井不動産)、横浜市西区の「エキサイトよこはまエリアマネジメント」(京急、相鉄、東急電鉄など)、大阪市北区の「梅田地区エリアマネジメント実践連絡会」(JR西日本、阪急電鉄、阪神電鉄、大阪メトロ)、福岡市博多区の「博多まちづくり推進協議会」(JR九州、福岡地所)などが挙げられている。


街全体を底上げする開発へ
実際にはもっと多く紹介しているのだが、見てわかるのはその地域を本拠地とする大手のデベロッパーや電鉄会社が中心になっているということ。
それが売っておしまい、短期的な費用対効果が優先されがちな住宅中心の開発との差につながる。本拠地で、あるいは自社路線沿線での開発となれば途中で終わらせることはできない。その企業が存続する限り、その地域、沿線に関わらざるをえないからだ。
となれば長期的に考え、開発エリア周辺の公共空間の質を高めるなど街全体の底上げを図る手が打たれる。資本力のあるチェーン店しか入れない開発にならないよう、周辺地域にあえて小規模な飲食店などを誘致、まちに多様性を生む努力なども行われる。
特に「エリアマネジメントによって可能になるゆとりある公共空間の整備」は大きなポイントだろう。
また、大手企業であれば開発がすぐに収益につながらなくても持ちこたえる体力もある。その結果が都心部での再開発を魅力的なものにしてきたといえるわけである。



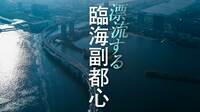



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら