10年で大変貌「官能都市ランキング」から考える「都市の魅力の作り方」《文京区、武蔵野市、金沢市は低迷。千代田区、中央区、豊島区が飛躍》
都心部だけでなく、今回の調査で躍進した立川市・昭島市、世田谷区などでも同様に地元密着の企業があり、長期的な展望に基づいたエリアマネジメントが行われている。
たとえば立川市には地元の大地主である立飛ホールディングスが開発したホテル、ホールや商業施設からなる複合施設「GREEN SPRINGS」があり、同社は周辺にアリーナやスケートリンク、ブルワリーなど地域の価値、楽しさを高める施設を作り続けている。同社は「たちきたエリアマネジメント」の事務局でもある。

郊外や地方都市はどうか?
では、逆に都市部郊外、地方都市の低迷はどう見るべきか。
もちろん、地方にも松本市や姫路市など新たに浮上してきた都市もあり、すべてが同じ状況にあるわけではないが、全体的な方向としては「引きこもるという言葉でまとめることができる」と島原さん。コロナ禍で引きこもったまま、その後も消費マインドが戻っていないというのである。
「地方都市の強みだったローカルフード体験や自然体験関連の消費は減ったままとなっており、最近ではさらに人口減少、高齢化が深刻化。消費と娯楽を支えてきたロードサイドのショッピングモールにすら閉店が増え始めています」(島原さん)


これについては直接的にダメージを与えたのはコロナ禍だったものの、地方都市の衰退の遠因としてはバブル期の成功体験と車が無いと生活できない街を作ってしまったことだったのではないかと島原さんは分析する。



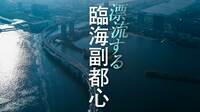



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら