健康情報のウソ・ホント!「なんだか体調が優れない」原因は体温調節の機能不全?
好感度の高い芸能人や有名人が出ていると、「あの人がおすすめしているから良さそう」「信頼できそう」と漠然と思ってしまいますが、「本当に良いものかもしれないし、でも違うかもしれない」という視点を常に持つことが大切なのです。
新しい成分ほど摂取のリスクを視野に入れる
たとえば、ビタミンCやビタミンDのように昔から使われている栄養素であれば、幅広い分野でのさまざまなエビデンスや知見もたまっていますが、新しい成分などは、新しければ新しいほど情報もないので、まだ海のものとも山のものともつきません。今は良くても10年後、20年後にどんな副作用があるか、誰も答えることはできません。
ですから、そういうものについてはある程度のリスクを視野に入れながら自己責任で摂るしかありません。ただ、アスリートの場合はドーピング検査があるので、サプリメントにしても風邪薬にしても、WADA(世界アンチ・ドーピング機構)と呼ばれる世界的なドーピングに関する機関が禁止しているものは摂ることができません。
WADAでは、人体に害があるものはドーピングの禁止薬物に指定していますし、日本アンチ・ドーピング機構(JADA)のホームページでは、何が該当するか検索システムで調べることもできます。
このように健康情報は巷に横濫していますが、まずはデータ元がしっかりしているのか、厚生労働省や学会など公的機関が認めているものなのか、営利目的の広告宣伝文ではないかをポイントに精査することが重要です。
本書では基本的に国内外の論文や、私の研究室で行ったデータをベースにしていますが、人間が生物としての普遍性を持つと同時に個別性という要素を持ち合わせており、アスリートを対象としたサポートでは、どちらの立場に偏っても良い成果は望めないと実感しています。
普遍性を追求する科学研究とそれだけでは解明できない個別性の問題を追及する実践研究とは、それぞれの限界を補完し合いながら、まさに車の両輪のように、互いの長所を活かし合う関係であるべきと考えています。





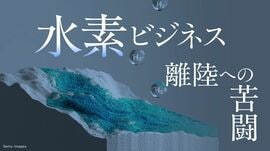







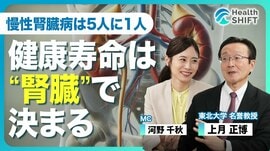

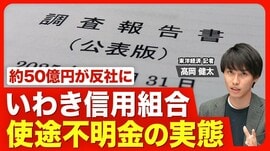
















無料会員登録はこちら
ログインはこちら