《ニュースの言葉を分かりやすく解説》ノーベル賞で注目「制御性T細胞」の知られざる凄み
その役目を担うのは、制御性T細胞の中でも特殊な「濾胞制御性(ろほうせいぎょせい)T細胞」というタイプの細胞で、この細胞が作り出すのがニューリチンと呼ばれるタンパク質です。ニューリチンは体にとって有害な抗体を作っている免疫細胞の増殖だけを抑え込む能力が確認されました。
もともとニューリチンは、神経細胞から分泌され神経細胞を守る役目を持つことが知られていましたが、その新しい働きが発見されたのです。
「警察」のような役割をしている
研究者たちは、遺伝子を改変してニューリチンを作れないマウスを作り、これに卵から抽出したアルブミンを注射したところ、アナフィラキシー反応で死ぬ確率が高まることが判明しました。(※)また、ニューリチンを作れないマウスは、生後初期の段階で、自己免疫疾患の原因となる可能性がある免疫細胞が増加することも確認されました。

さらに、実際に自己免疫疾患に陥ったマウスにニューリチンを注射することで、免疫の誤作動を治療でき、マウスの健康が維持できることも示しました。この結果は、濾胞制御性T細胞とニューリチンが、有害な免疫細胞を取り締まる「警察」のような役割をしていることを示唆します。
免疫の暴走を解決するには正常な免疫能力を奪わないまま、問題を起こしている免疫だけを狙い撃ちする必要がありますが、そのような都合のいい方法は簡単には見つかりません。
これまでは、ステロイドや免疫抑制薬といった免疫力そのものを弱体化させる治療が行われてきましたが、ニューリチンの役割がわかったことでアレルギーや自己免疫疾患をニューリチンの注射薬で治療できるようになる日が来るかもしれません。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

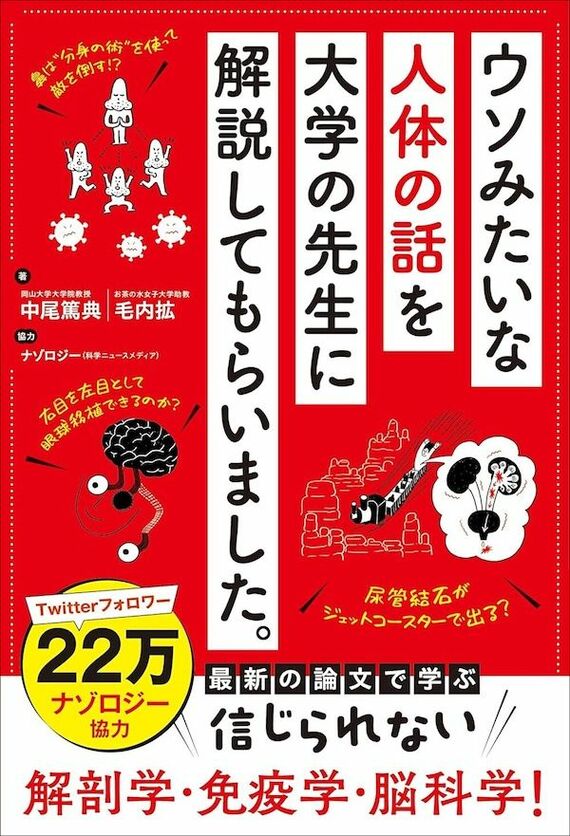






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら