「WBC」ネットフリックス独占中継に批判の声が殺到する、日本特有の根本的な理由
欧米では「有料で当たり前」という考えが早くから浸透していたが、日本では地上波の広告モデルが機能し続けたため、視聴者が積極的に料金を支払う理由が見出しづらかった。BSやCSが登場しても契約数が伸び悩んだ背景には、こうした文化的土壌があった。
しかし、その「恵まれすぎた環境」も少しずつ変わっている。若者を中心にテレビ離れが進み、地上波局は広告収入の減少に直面。スポンサーの出稿は縮小し、制作費の削減が避けられず、安価な再放送や低コストのバラエティに依存する傾向が強まっている。
国内地上波はグローバル配信大手に敗れた
一方で、配信大手は世界市場を背景に巨額の資金を投じ、映画、ドラマ、スポーツといったジャンルに戦略的に投資している。今回のWBC放映権料が前回の5倍に跳ね上がったとされるのも、そうした資本力の差を如実に示している。国内市場だけに依存する地上波には到底支払えない金額を、グローバル展開するネットフリックスは十分に負担できるのだ。
結局のところ、今回のWBC独占配信は単なる放送権の問題にとどまらず、日本のテレビ文化全体の転換点を象徴する出来事である。長らく「無料で誰にでも届く公共的メディア」として君臨してきた地上波テレビは、資本力と国際展開を武器にする配信大手に主導権を奪われつつある。
これは「地上波テレビの終わりの始まり」を鮮明に示す事件であり、テレビが今後どのような新しい役割を模索できるかが問われている。このまま何もできなければ地上波は緩やかに衰退し、時代に取り残されることになるだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

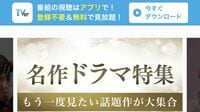





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら