「思い出される2007年の偽装ラッシュ」「コンビニチェーンの闇か…」ミニストップの消費期限偽装が示す《コンビニ経営の問題点》
現在のコンビニエンスストアチェーンの店舗はフランチャイズ店となっている。この制度は、フランチャイズオーナーにリスクを負わせつつ、多くの制約も課すやり方として、これまでも問題視されることが多かった。
個店の利益を上げるという局所最適な行為が、コンビニチェーンの信用を毀損するという結果となり、全体最適を損なってしまっているのだが、その多くはフランチャイズ制というコンビニ経営の構造に負っているように見える。
2019年にローソンの埼玉県の2店舗で、店内調理の一部商品の消費期限の改ざんが判明し、両店との契約を解除、閉店するという事態が起きている。
この2店舗はフランチャイズ店で、同じオーナーの経営であったという。個別の事案ではあるが、今回と類似する問題が別のコンビニチェーンでも6年前に起きていたということは、思い出しておくべきだ。
ミニストップの対応は適切だったのか?
2007年前後に起きた食品偽装問題の多くは、内部告発によって発覚している。その点で、企業内の自浄作用が働いていなかったと言えるだろう。
今回のミニストップの事案は、第三者による定期調査によって発覚したという。また、公表後に全国約1600店の全店で店内加工のおにぎりや総菜、弁当の販売を中止するという判断も行っている。そうした対応は自浄作用が働いていると、評価できる。
現時点で健康被害は起きていないことも不幸中の幸いだった。
一方で、少なからず疑問も湧いてこざるをえない。
偽装行為は数年前から行われていたというが、どうして今まで発覚しなかったのだろう。また、複数店舗に広がっていた要因も解明する必要があるように思う。





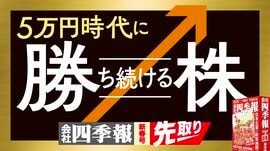


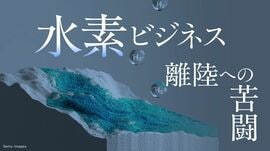





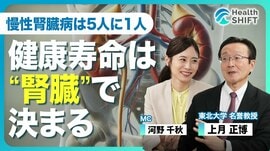







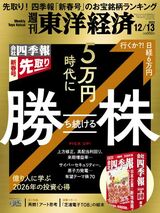









無料会員登録はこちら
ログインはこちら