「思い出される2007年の偽装ラッシュ」「コンビニチェーンの闇か…」ミニストップの消費期限偽装が示す《コンビニ経営の問題点》
しかしながら、今回のミニストップの偽装は、関西を中心とする多くの地域の23店舗で起きている。企業ぐるみで行われていたものではないとはされつつも、これだけ広範で起きていることを考えると、大きな背景となる要因があるはずだ。
ミニストップの事案は、現代ならではの新たな要因によって発生したと考えられる。具体的は、下記の2点が大きな要因になっていると考えられる。
2. コンビニ経営の構造的な問題
今回の件は「ミニストップ」固有の問題ではない
TBSの報道によれば、ミニストップの社員は「1時間でも廃棄を遅らせたいという店舗が多かった。どうしても、廃棄時間を少しでも、という理由でやってしまったところが多いと聞いています。本社は、廃棄を減らせなどの通達はしていません」と述べているという。
食品廃棄は店舗の収益悪化につながるため、オーナーからすると、できるだけ回避したいところだ。昨今では「フードロス削減」の社会的潮流が起こっており、消費期限や賞味期限にさほど厳格になる必要はない――という風潮も生まれている。
筆者の実家は飲食店を経営しており、知り合いにも飲食店経営者がいるが、食材の原価が上がり、利益を出すのが難しくなっている。そうした中で、食品のロスを削減することは、以前に増して重要な経営課題となっている。
問題行為ではあるが、改ざんしやすい店内調理メニューで、つい消費期限のシールを貼り替えてしまった心理は、上記のことを鑑みると理解はできる。
そこに、もう1つの「コンビニ経営の構造的な問題」が加わってくる。





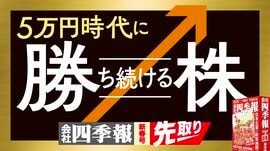


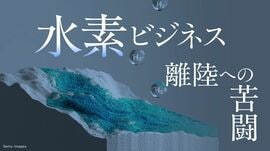





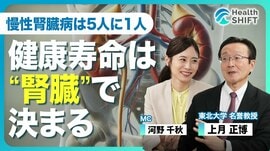







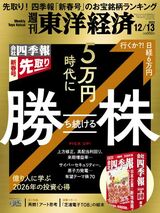









無料会員登録はこちら
ログインはこちら