寄付者の多くはビジネスリーダーなどの富裕層で、1人当たりの寄付金額も高い。年に一度、ホテルで開かれるチャリティーガラパーティーには約300人が集まる。紹介によって参加者は増え、毎年の寄付金額は伸びている。
ただ、まだ伸びしろは大きい。「日本では、困っている人を助ける活動は知られているが、国や政府が作った枠組みの中でやるしかないと思われがちだ。人々には制度や政策を変える力があるという認識を広めることも大事だ」(土井代表)。
日本企業の意識の高まりは追い風になりうる。これまで、調査に関する情報提供を日本企業に依頼しても、協力を受けられないことも多く、HRWに対する企業からの寄付はごくわずかだという。
日本のNGOの重要性が増している
現在は、欧州を中心に「ビジネスと人権」への対応が義務化されており、日本企業も人権問題に積極的に対応しなければ事業活動においても支障が出る。「意識の向上が寄付に結びつくかはわからないが、われわれが調査して報告する情報の必要性は高まるだろう」(土井代表)。
逆風はトランプ政権によるアメリカの対外支援の縮小だ。政府資金を受け取っていないHRWの資金面に直接的な影響はないものの、国連やほかの団体も民間からの資金調達を強化しているため、獲得競争は激しくなっているという。
食料の提供など緊急性の高いサービスを提供していた団体も資金難に陥っており、それらの団体への寄付が優先される傾向にある。人権調査で協力してくれる現地のNGOや活動家も資金繰りが厳しく、現地での聞き取り調査も難しくなっている。
HRWは、日本や欧州各国の政府に対し、これまでアメリカが資金援助をしていたNGOの支援を要請している。国際秩序が混乱する中、人権問題を告発し続けるHRWの存在感は増している。
以下では、HRWの概要や企業との連携などを紹介する。

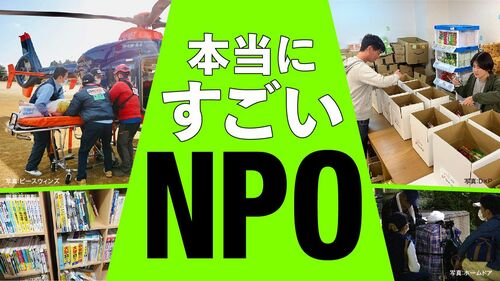






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら