人気上昇の「ミャクミャク」
あれほど評判が悪かった公式キャラクター「ミャクミャク」が急速に人気を獲得し、来場した個人によるSNSの投稿を通じて各国のパビリオンが再評価され、万博を効率良く楽しむための「攻略法」の発信と実践が大流行した。
この展開も東京五輪にそっくりだ。五輪開催直前の世論調査で78%が「開催すべきでない」と回答したが、メダルラッシュが報じられ始めると礼賛一色に覆い尽くされた。
空気に流されやすいと言えばそれまでかもしれないが、それ以上に国民が手っ取り早く共有できるイベントについて、潜在的なニーズが相当高かったのではないかと思えてくる。要は誰もが乗っかれる鉄板ネタだ。
暗い未来ばかりを想起させられる世相に嫌気が差しているからこそ、「わたしたち意識」を充填してくれる国民的コンテンツで気分を上げようとするのだ。
けれども、「演目がつくりだす共通の幻想は、公演の興奮がさめると雲散霧消する」(同上)ものでしかない。東京五輪のときもそうだったがイベントは必ず終わりを迎える(そして、汚職・談合事件が明るみになった)。大阪・関西万博も10月には閉幕する(隣地では日本初のカジノを含む統合型リゾート施設の建設が賛否を呼んでいる)。
祭りの後には、往々にして虚無感を伴うものだ。その一方で、「祭り便乗資本主義」とでも名付けたくなるような、その熱狂を尻目に自己の利益を最大化しようとする者がいるのもまた事実である。
しかしながら、長期停滞が日常風景となり、現実が色あせる中で「それでもないよりはまし」という声なき声もまた痛切なもののように思えるのだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

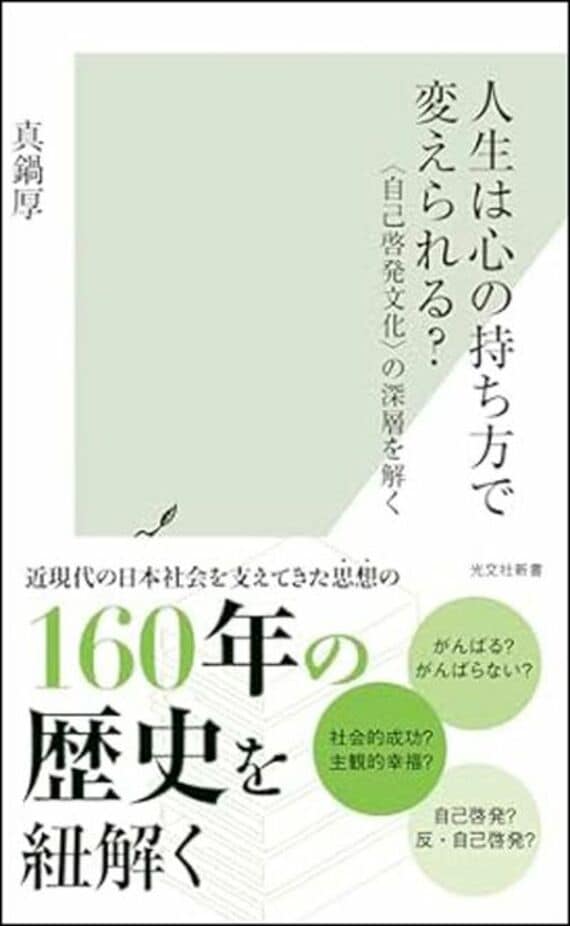































無料会員登録はこちら
ログインはこちら