とくに、中長期試算の前提となるのが、マクロ経済に関する年央試算である。年央試算では、当年度の下半期と来年度の経済成長率や物価上昇率などの見通しを示すこととなっており、それが中長期試算の土台となる。別の言い方をすると、年央試算が示されないと、中長期試算は示せないといってよい。
今回の中長期試算は、アメリカの関税措置の影響などを踏まえ、前回の2025年1月試算に比べて、2025年度と2026年度の経済成長率は低くなることを織り込んだものとなっている。ただ、中長期的には前回1月試算とおおむね同様の成長率で推移するという試算結果となっている。
では、中長期試算で1つの注目点となっているプライマリー・バランス(基礎的財政収支)はどうなったか。
結論からいうと、2025年度と2026年度の国と地方のプライマリーバランスは、前回1月試算と比べて改善するという試算結果となっている。
プライマリーバランスを急回復させるモノ
前回1月試算は、2025年度は4.5兆円の赤字、2026年度は2.2兆円の黒字となると見込んでいたが、今回8月試算では、2025年度は3.2兆円の赤字、2026年度は3.6兆円の黒字となるという結果である。
今年度から来年度にかけてプライマリーバランスが急速に改善して、2026年度には目標としているプライマリーバランスの黒字化が実現するという見込みである。
中長期試算では、かつて経済成長率を高めに見積もっているから、収支改善は取らぬ狸の皮算用であるかのように批判する向きもあったが、2026年度までの試算結果は、(成長率が高い順に)高成長実現ケース、成長移行ケース、過去投影ケースと3つある、どのケースでも大差はないから、経済成長率を高めに見積もっていることでプライマリーバランスの黒字が拡大するということではない。
では、どうしてそれほどにまで改善するのか。
内閣府の分析によると、そもそも2024年度の国の決算で、予算の不用や繰り越し、税収の上振れが実現しており、それを今回8月試算には反映している。これが、試算の発射台として収支が改善するところに効いている。

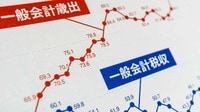
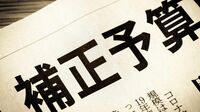




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら