
2026年度の予算編成に向けて、8月末で各省庁からの概算要求の提出を締め切った。2026年度予算編成で注目点の1つは、2026年度診療報酬改定がどう決着するかである。
物価高騰の折、費用の増加に直面して経営難に陥る医療機関が出てきている。このまま医療サービスの価格(診療報酬単価)を不十分にしか上げないとなると、今後医療機関の経営破綻の増加も懸念される。
ただ、診療報酬を大きく引き上げるとなると、医療保険料も大きく負担増となる。7月の参議院選挙でも、現役世代の負担軽減が取り沙汰されており、医療機関の経営が苦しいから医療保険料を大きく上げてよい、というほど単純な決着にはならないだろう。
高齢者の負担増だけでは解決できない
確かに、1つの解決策はある。
医療費の半分近くを使っているのは高齢者である。高齢者は、現役世代よりも保険料負担が相当軽くなっている。そのうえ、患者負担割合も、現役世代は3割自己負担だが、高齢世代は多くが1割自己負担や2割自己負担である。現役世代の平均的な課税前収入を持つ高齢者でも、2割負担や1割負担になっている。
この世代間不公平を改めることは、診療報酬をきちんと出しつつ現役世代の負担軽減に資するだろう。
しかし、高齢者の患者負担や保険料負担を増やすことは、問題の解決する方向には助けとなるが、それだけでは問題は解決できない。
特に、冒頭に述べた医療機関の経営難の解決に向けては、診療報酬のメリハリ付けが不可欠である。経営難に直面している医療機関もあれば、コロナ禍でいったん減った患者が戻ってきて物価高の中でも利益率を上げる医療機関もある。
だから、物価が3%上がっているといって、診療報酬単価をすべてメリハリなく一律に3%上げては、問題の解決にはならないことは明らかだろう。

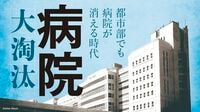





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら