こうした費用の増加を、診療報酬単価に半ば機械的に反映できていれば、これほど騒がれることはなかったかもしれない。しかし、わが国の診療報酬では、「資本コスト(キャピタル・コスト)」とか「ドクター・フィー(医師の技能や仕事量に対する報酬)」という考え方を厳密に採用しているわけではない。昭和の頃からずっとそうである。
だから、わが国の診療報酬の制度設計では、ある入院患者が病院施設をどの程度使い、それに基づいてその費用をどの程度負担してもらうか、という発想が希薄である。
そうなると、入院患者を受け入れた病院が、その診療行為から得られる医業収入があっても、その収入をどの程度機器や設備の関連費用を賄うのに充て、どの程度医療従事者の給料に充てるかは、病院の経営判断次第、ということになっている。
特に、直近での状況では、まさに機器や設備の関連費用である「資本コスト」が増加している。
他方、無床診療所は、大きな手術をするわけでもないから、機器や設備をほとんど使わず、それらに関する費用の増加はほとんど関係ない。
こうした状況の下で、メリハリなく一律的に物価上昇分を診療報酬に加算したとしても、医療機関の経営難の問題が解決できるはずはない。むしろ、一律に上げた分だけ、医療保険料の負担増に直結する。
診療所は利益率が改善している
しかも、前掲の建議では、診療所における1受診当たりの医療費が、全体でみると、コロナ禍以降に急増していることを指摘している。また、病院における患者数は減少傾向にある一方で、一般診療所における患者数は足元で増加しており、1996年以降で最大となっている。そして、外来診療の受療率で見ても、足元ではコロナ禍前と遜色のない水準にまで回復している。
厚生労働省が、診療報酬について議論する中央社会保険医療協議会(中医協)に8月27日に提出した資料によると、医療法人立の医科診療所の2023年度の医業利益率は、平均値6.9%、中央値4.1%といずれもプラスとなっており、医業利益の黒字割合は66.6%と過半数を超えているという。前述の傾向が利益率にも現れている形だ。
その観点から、2026年度診療報酬改定では、病院と診療所の診療報酬において、どのようにメリハリが付けられるかがこれまで以上に問われよう。病院と診療所が、地域医療において担っている役割にふさわしいメリハリ付けが求められる。
もちろん、病院といえども、消耗的な病院間競争の結果、過剰に医療機器を購入しているところがある。これを機に抜本的に改めることが経営難の克服につながるから、過剰設備を改めてもらうことは当然である。
診療報酬を一律的に引き上げなければ医療が崩壊する、という言説に乗ってはならない。メリハリを付けた結果、上げてもらえなかった当事者がヘソを曲げるのが怖いから、一律的に引き上げた方が、政治家や関係当事者は楽だろう。
しかし、彼らに楽をさせれば、そのツケは税負担、医療保険料負担や患者負担の増加という形で回ってくることを忘れてはならない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

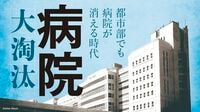





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら