6月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太方針2025)」には、医療界が注目した文言が盛り込まれた。
一般会計の社会保障関係費について、「高齢化による増加分に相当する伸びにこうした経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算する」。「こうした経済・物価動向等」とは、賃上げや物価上昇が起きていることを指している。
これまでの一般会計の社会保障関係費は、医療・介護については、基本的に「実質的な増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめる」との方針で予算編成が行われてきた。そこから「加算する」と記されている。
だからといって、メリハリなく一律的に加算するということが許されるはずはない。そして、一律的に加算したのでは、前掲の問題の解決をむしろ妨げる。
インフレで費用が増えた医療機関とは
解決のカギはどこにあるか。
それは、5月27日に財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会が取りまとめて財務大臣に手交した建議「激動の世界を見据えたあるべき財政運営」にある。
同建議には、診療報酬改定に向けたさまざまな改善策が記されているが、本稿では前掲の問題の解決に資する部分のみを取り上げよう。
結論から言えば、病院と診療所の対応を分けることである。
ちなみに、わが国では、病床が20床以上ある医療機関を病院と呼ぶ。診療所にも、入院患者を受け入れられる病床を持つ診療所(有床診療所)もあるが、大半は受け入れる病床を持たない診療所(無床診療所)である。
物価高で費用の増加に直面している度合いが高いのは、病院である。病院は、入院患者を受け入れ、高度な手術を行えるから、医療機器や給食施設、さらには自家発電設備も備えている。無床診療所とは根本的に異なる。
そうなると、機器や設備に関する費用が物価高騰によって増加していて、それを医業収入で賄えないとなると、経営難に陥る。

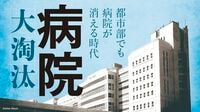





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら