「思いがけないお申し出でびっくりしております」絶滅危惧種イヌワシ研究の第一人者が驚愕した理由
一関市農林部林政推進課の地域林政アドバイザー、菊池宏さん(64歳)に市の自伐型林業への取り組みや協議会を構成する下京津畑共有山組合について聞いた。
それによると、市としての本格的な取り組みの第一歩が地域おこし協力隊の募集で、加藤純さんら3人が採用された。
菊池さん自身は長く森林組合に勤め、自伐型林業をやや懐疑的に見ていた。いまは、「消滅集落まっしぐらのスピードをちょっとでも遅らせることができれば」と期待している。
下京津畑共有山組合は、もともと馬を放したり、茅を刈ったりするための入り会いの山だった。現在、25人の組合員が共有する。広葉樹のナラを伐採し、木炭を生産していた。原木シイタケの栽培に力を入れようとした矢先、2011年の東日本大震災・福島原発事故がおきてできなくなった。
まぶちの森と下京津畑共有山組合のあわせて180ヘクタールの山林で、どのようにイヌワシの餌場づくりと林業を行うのか。今後、調査を重ねて計画をつくり、環境省の自然共生サイトへの登録を申請する予定だ。
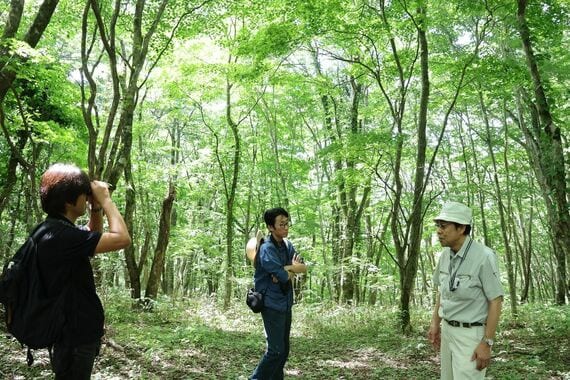
岩手県のイヌワシのレッドゾーン公表後、巨大風車群の建設ラッシュへの影響は?
岩手県環境保全課によると、現時点で環境影響評価手続きを進めている風力発電所の建設計画は、27事業(県境付近の県外の事業を含む)、最大出力では計318万8500kWに及ぶ。このうち、9事業の事業区域がイヌワシのレッドゾーンにある。
2024年3月のレッドゾーン公表の影響はあるのだろうか。「公表後に複数の事業者から問い合わせや相談があった。新規の事業を計画している事業者の中には、計画地がレッドゾーンにかかることを踏まえて計画を検討し直しているところもある」(環境影響評価・土地利用担当主任主査)という。
また、調査期間や調査内容の見直しを行っている事業者もあり、「皆さん、慎重になっている。環境アセス手続きが当初の予定に比べ遅くなり、全体的に止まっているかのようだ」と見る関係者もいる。
環境アセスメント制度といえば、これまで希少な鳥類に関しては「ほかの場所に飛んでいくから」、植物に関していえば「移植すればよい」ので影響は少ない、とするケースが目についた。希少動植物への影響を軽視する傾向が変わっていけばよいと思う。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら