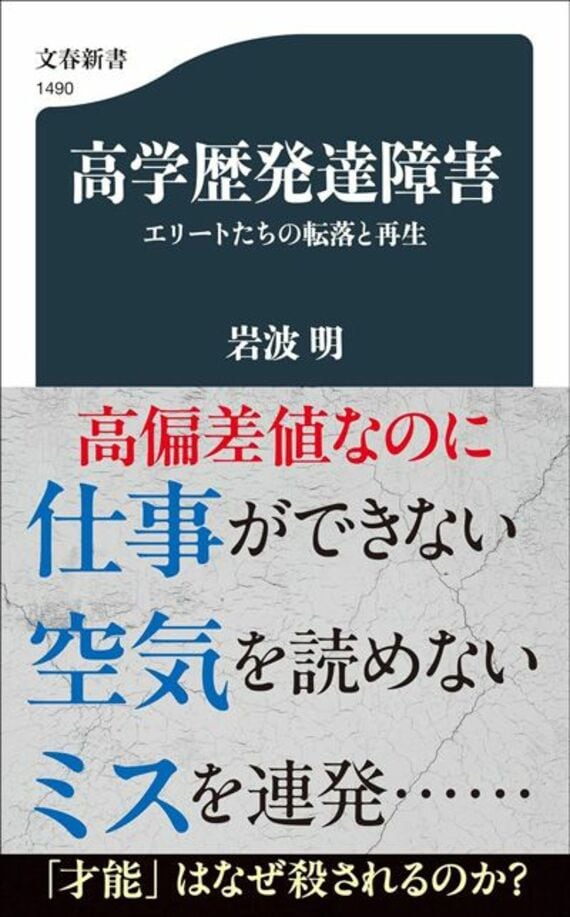”受験エリート”からコースアウトする中高生が増えている。「学校への不適応」をもたらす4つの要因とは?”規則の厳しさ”が誘発することも
思春期になると、発達障害、特にADHDにおいては、睡眠、覚醒リズムが不安定になることが多く、不眠もみられるが、過眠となることも珍しくない。このため、学校に通うこと自体が困難になりやすい。
私立の進学校においては、授業の進み方が早く、また毎日のように多くの課題が与えられる。ASDの生徒は関心がない勉強にとりかからないことがみられる一方で、ADHDの生徒は「問題の先送り」をしてしまう特性から、課題がこなせないことが珍しくない。
現場の教師の対応、態度も重要である。発達障害を持つ子供は、平均値的な行動パターンからずれた振る舞いをすることが多いが、これに対して教師が共感的に受け入れるのか、排除しようとするかによって、生徒の適応は大きく異なってくる。
逆に言えば、これらの点に学校や教師がうまく対応できれば、発達障害の特性を持つ生徒のドロップアウトを防ぐことは可能であり、安定した学校生活を送れる可能性もある。
多くの問題は発達障害の特性に起因するもの
また家族の側としては、子供の「だらしなさ、やる気のなさ」を繰り返して責めてしまいがちである。もちろんそれらの問題を指摘することは教育上必要ではあるが、多くの問題は発達障害の特性に起因するものであることを認識してほしい。
また不適応によって不登校が続く場合、無理に学校を継続するよりも、リセットして通信制などに転校することが良い結果につながることは少なくない。手をつくしてもうまくいかない場合は、いったん撤退して考えなおすことは必要である。
中学、高校は最終ゴールではない。家族においては、大学や大学院に進学し社会人として生活することを、目標としてイメージすることが必要である。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら