"東京ドーム4個分"の都有地が未処分・・・臨海副都心の誤算 構想が動き出して40年、巨大な「人工海上都市プロジェクト」は失敗だったのか
長期的な視野で見ると、開発が進まなかった根本要因は、臨海副都心の構想段階から社会情勢が大きく変化したことにある。江戸時代から埋め立てによる土地拡張を続けてきた東京の造成地に、人工都市を整備する巨大プロジェクトが発表されたのは、バブル期前夜の1985年だった。
臨海副都心プロジェクトに関わった先述の平本氏によると、1980年代に発表された東京都の長期計画において、東京の都市構造を「多心型」に転換する方針が示された。オフィス需要の急拡大が見込まれていた当時、都心以外にいくつかの副都心を設けて、業務機能の一極集中を是正する狙いがあったという。こうした文脈で1986年、広大な土地を擁する臨海地区に7番目の副都心として白羽の矢が立つことになった。
しかし、大規模ビジネスセンターとしての機能を期待された臨海副都心プロジェクトに、想定外の誤算が生じる。1991年ころから本格的に始まったバブル経済の崩壊だ。それまで企業の進出合戦の様相を呈していた状況は様変わりし、「オフィス需要がしぼんで、建物はチョボチョボとしか立地しなくなった」(平本氏)。
規制緩和がもう1つの転機に
バブル崩壊に加えて、もう1つの大きな転機をもたらしたのが、2002年に小泉純一郎政権下で制定された都市再生特別措置法だ。
バブル崩壊後の地価下落に歯止めがかからない中、民間事業者を主体に都市の再生を進めることを目的とし、「緊急整備地域」に指定された場所については、デベロッパーが自由に開発を進めやすくなったとされる。都内でも、都心部や臨海地域をはじめ複数の場所が指定を受け、湾岸部では豊洲や晴海といった地域で高層ビルの開発が急速に進んでいった。「都心から遠く、公共交通もまだ弱い臨海副都心にオフィスを作る必要性がなくなり、今は臨海副都心からみて、(周辺地域が)タワーの山になっている」(平本氏)。
初期構想から40年が経った今、平本氏は「都が都市計画を放棄したわけだから、放棄する前の『臨海副都心』という名称はいらない。もう一度違うコンセプトで再出発して、今以上に魅力ある地域、東京にとって必要な場所として考え直していくのがいいのではないか」と語る。
時代に翻弄された過去の誤算を映し出す、海上都市の巨大未処分地。取り残された土地を“貴重な遺産”として、新たな未来をどう描いていくか。真剣に検討すべき時期にさしかかっている。
詳報記事はこちら
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

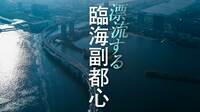





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら