人気サッカー漫画『ブルーロック』に学ぶ《メタ思考》の仕組み ミスが許されない時代を生き抜く思考法とは?
振り返れば昭和という時代は、社会も人々も自分本位に、アクセルを踏み続けていたようなもの。非常に「雑」な社会でした。
言動1つとってもそう。頭に浮かんだことをすぐに口にし、やりたいようにやる。周囲がそれをどう感じようとお構いなし、という感じが強かったように思います。
ますます高まるメタ思考の重要性
一方、現代は、法律が「全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を謳っているように、私たち1人ひとりが、「人を傷つけない」ことに特段の注意を払わなくてはいけない時代になりました。
とくに人間関係においては、互いの距離感を繊細のうえにも繊細につかんで行動する必要があります。
自分ではふつうに接したつもりでも、ハラスメントと指摘される場合だってあります。
だから、メタ思考の重要性が高まっているのです。
自分の言動によって人がイヤな思いをするのではないか、傷つくのではないか、といったことを感じ取ることは、メタ思考なくしてできないことですからね。
加えて「SNS時代」に突入した現代は、常に「自己チェック機能」を働かせることが、ますます重要になっています。
たとえば、ちょっとうかつな発言をしてしまうと、すぐに「はい、アウト」とレッドカードを出されます。
それどころか、一切の悪気なくつぶやいた一言でも、強烈なバッシングを受けて、社会的生命を抹殺されるような恐怖を感じるくらい、痛めつけられることすらあります。
そうならないためには、日常の会話やメールのやりとりでもそうですが、とくにSNSに投稿するときは、頭に浮かんだことを思いつくままにつらつらと書いてはダメ。
ワンクッション置いてメタ思考を働かせて、「不快に思われる可能性はないか」「傷つく人はいないか」をチェックしなくてはいけません。
後になって「冗談だよ」なんて言い訳したって、ネットに流したら最後、もう取り返しがつかないのです。
SNS時代の言動で一番重要なのは「自己チェック機能」を持つこと。
そのために、メタ思考の重要性がますます高まっているのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

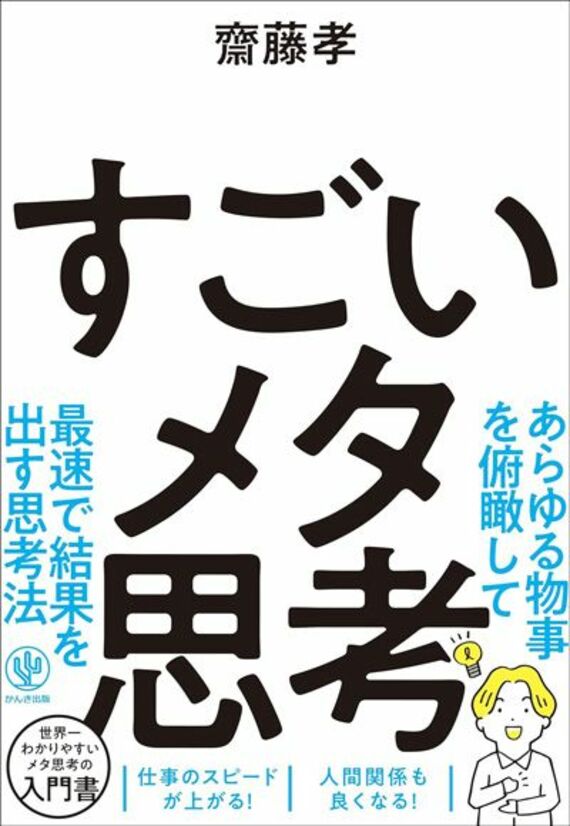






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら