「給与は変わっていないのに手取りが減ってる…?」今更聞けない「給与明細」の読み解き方を≪2億円の資産を築いたブロガー≫が解説!
続いて、②控除(総支給額から差し引かれる金額)の中身を見ていきます。健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険が代表的な4つの社会保険で、所得税と住民税が税金になります。なお、社会保険は労使折半なので、企業がおおよそ半分を支払っています。
社会保険が正確にどのようなものか、ご存じない方も多いかもしれません。
健康保険は、国民健康保険の企業版で、病院の診療を受けたり、薬局で処方薬を購入する時に自己負担が3割になるという、一番馴染みがあるものです。
厚生年金保険は、公的年金制度の1つで、国民年金を1階部分とした時に、2階部分とされているものです。原則的に65歳から受給される年金を、イメージでは前倒しで支払っているわけですね。「イメージ」としているのは、今の日本の年金制度は、現役世代の支払いを高齢者の年金にあてる仕組みだからで賦課方式と言います。
この2つが社会保険料の大半を占めているので、残りの介護保険、雇用保険はそういうものがあると認識しておいてもらえれば大丈夫です。簡単に説明しておくと、介護保険は高齢者の介護を行うためのもの、雇用保険は失業時に失業給付やハローワークでの求職支援を受けるためのものです。
給与は変わっていないのに手取りが減っている理由
次に税金ですが、所得税は、給与所得から一部控除を除いた課税所得に対して、最小5%、最大45%の累進課税で税金がかかるものです。少し計算が複雑ですが、給与が上がれば上がるほど、増えた部分の税率が上がっていくと理解してもらえれば大丈夫です。住民税も同じく、給与所得から一部控除を除いた課税所得に対して、こちらは一律10%支払います。給与が上がってもずっと10%です。
こうして、①支給の合計額から、②控除の合計額を除いたのが、差引支給額=手取りとなります。




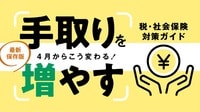


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら