「人間はなぜ働く必要があるのか?」狩猟採集社会まで遡って、働き方の歴史を考えてみる
そして都市部では、新たに誕生した職業に基づく共同体も生まれます。大工、石工、建築家、技師、下水処理人など新しい専門職が誕生すると同時に、大規模な集団(都市)の秩序を維持する官僚、裁判官、兵士なども必要になります。
農耕社会がもたらしたもの
そのなかで、職業と一体化した社会的アイデンティティ(職業内での協力・支え合いの関係)も生まれていったのです。
宇 野「農耕社会の生産性の高さが、都市とか専門的な職業を生む源泉となったんですね。働き方も、狩猟・採集とか農耕だけでなく、新しい専門的な職業が生まれていくもととなったのが、農業が生み出す余剰だったというのも興味深いです」
真 由「でも、その生産性や余剰を生み出す農耕作業って、そこで働く人たちに過酷な労働を課すもので、身体的にも大きな負荷がかかるものだったんですよね。こんな辛い思いをするくらいだったら、元の自然な生活に戻ろうってならなかったんでしょうか」
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

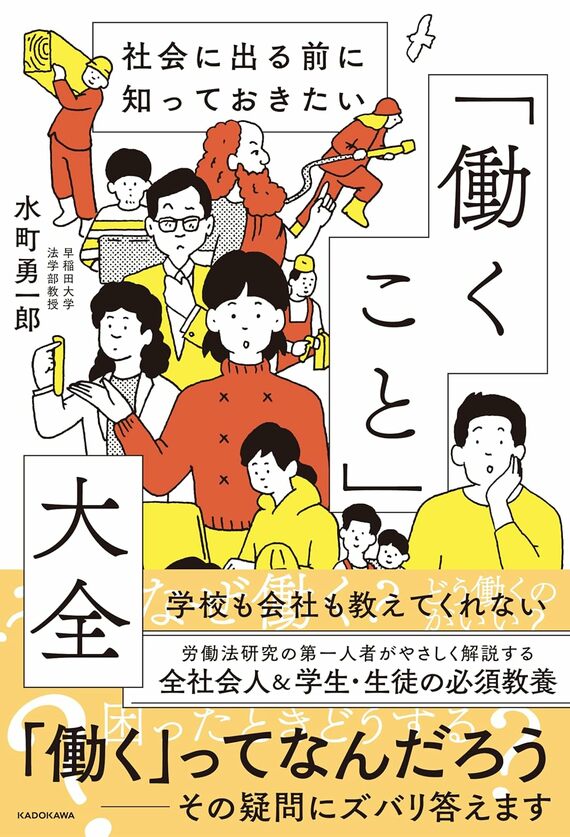






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら