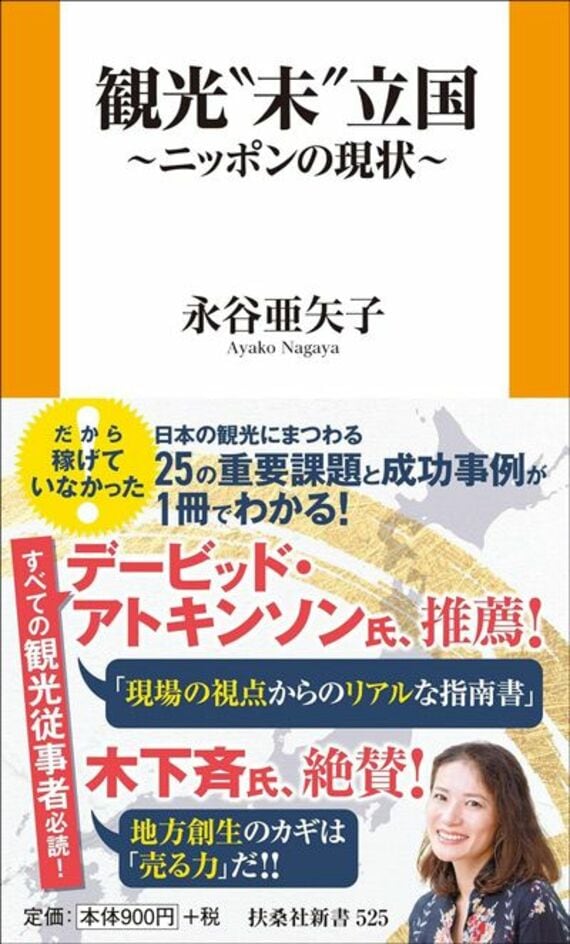「地域のホンモノ体験」こそが価値を持つ
永谷亜矢子(以下、永谷):1次産業の「6次産業化」。これこそが、今後の観光における重要なキーワードになると考えています。
6次産業とは「1次×2次×3次=6次」という造語なのだけど、農業や水産業などの1次産業者がただ原材料をとって流通に乗せるのではなく、食品加工や流通販売などにも業務展開する経営形態を指します。
実際にある事例でいえば、漁師さんと一緒に船に出て、漁体験をしてもらって、港に帰ったら新鮮な海鮮丼を出すとか。
あるいは早朝のトウモロコシ畑で収穫、そのままサウナに入ってBBQを楽しめる観光コンテンツを提供するとか。
こうした「ホンモノ体験の力」は偉大です。地域に新たな付加価値を生み出し、また「高付加価値化」にもつながるはず。
鈴木信吾(以下、鈴木):とてもよい考え方ですね。
「うちには名所旧跡もないから、インバウンド誘致は不可能」と考えてしまっている地域は少なくない。一方、地域はむしろ1次産業の宝庫といえます。
「観光コンテンツがない」と最初から諦めるのではなく、「あるものをいかにして観光コンテンツに変えるか」という工夫や発想の転換が必要不可欠です。