不満のはけ口?医療者がSNS「不適切投稿」の背景 海外では「手術を生中継した」医師が免許剥奪も
知人で、千葉大学病院とは違う大学病院に勤める山本知佳看護師は、「医師への報告がしにくい環境(医師の威圧感がある対応、看護師を下に見るような態度など)や、再発防止のためのインシデント報告が“犯人探し”になりやすいシステムなどは、どこの医療機関でもあると思う」と言う。
このような環境下で、看護師が不満のはけ口を求め、SNSに投稿する人がいてもおかしくない。今回のケースがもしアメリカで起こっていたら解雇だろう。千葉大学病院も重い処分を科すのではないか。
一方、こうした問題が表沙汰になることで、一定の抑止力にはなると筆者は考える。ただ、それだけでは不十分で、看護師の過剰労働やストレスを緩和する具体的な仕組みが必要だ。
この点についても、世界では試行錯誤が続いている。
例えば、アメリカでは看護師の労働環境を客観的に評価しようとする試みが進む。その1つがアメリカ看護師認証センター(ANCC)が実施する「マグネット認証」で、看護師の労働環境や教育機会、キャリア支援体制を評価する。
この認証を受けた病院では看護師の離職率が低いことが知られており、2024年1月時点で、アメリカ全体の約9.8%の病院が、マグネット認証を取得している。
1人の看護師が受け持つ患者の数
政府が介入している国もある。オーストラリアのビクトリア州では、2000年に看護師対患者比率を法的に定める制度が導入され、一般病棟の日勤帯では、看護師1人あたり患者4人(1:4)の比率が規定された。看護師の労働環境改善と患者ケアの質向上を目的としたものだ。
ちなみに、日本は急性期病院の一般病棟ですら、看護師1人あたり患者7人(1:7)だ。一般病院は1:10、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟は1:13。これらが診療報酬上の基準として設けられている。
看護師を増員するためには、財源的措置が必要だ。つまり、金がかかる。このあたりは国民的な議論が必要だが、このような情報が社会と共有されることはほとんどない。
今回のSNS騒動が、そのきっかけになればと筆者は思っている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



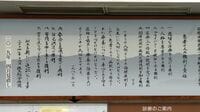



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら