初心者でも失敗しない好みのワインの選び方 高いボトルだからおいしいとは限らない
もしかすると、そういったこだわりワインを入門段階で飲むと、がっかりしてしまうかもしれません。理由は、高価だと期待値が高まりすぎてしまうから。そして高価なワインはたいてい玄人向けの味に仕込まれており、味が複雑でわかりにくい可能性があるからです。
少しずつ経験を重ねてランクを上げる
「Trading Up(トレーディングアップ)」とは、少し上のランク(もしくは高いもの)に乗り換えることです。たとえば1000円から1500円のワインに、1500円から3000円のワインに……といった具合に、少しずつランクを上げていきます。
まずは安価なワインからスタートして、舌の成長とともに徐々に高いワインにチャレンジすれば、経験によってワインのよさが無理なくわかるようになるかもしれません。
1000円前後のワインをつくっているワイナリーを訪問したことが何度かあります。たいてい醸造施設は大きく、衛生的で、醸造器具がたくさん並んでいます。量産しているにもかかわらず、ワインを試飲すればどれも美味しく、つくり手は「バランスを大切にしている」と口を揃えて話します。
この価格帯のワインがすごいのは、初心者から玄人まで誰が飲んでも美味しいこと。すべては「バランス」に集約されます。酸っぱすぎず、渋すぎず、重たすぎず、そしてフルーティー。こういった味わいを嫌う人はほとんどいないでしょう。実は、この誰が飲んでも美味しいワインを量産することが一番難しく、つくり手の手腕が試されているのです。
この価格帯のもうひとつの魅力は、たいてい有名品種から仕込まれていること。シャルドネやカベルネ・ソーヴィニヨンのように、一度は耳にしたことのある品種ならば売り場で選ばれやすいからです。基本品種を覚えるのにちょうどよい、教科書的なワインが多く揃っているのもこの価格帯の特徴です。まずは1000円前後のワインから始めてみませんか。















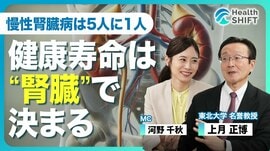






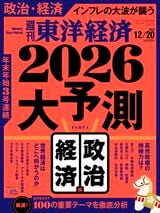









無料会員登録はこちら
ログインはこちら