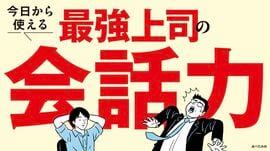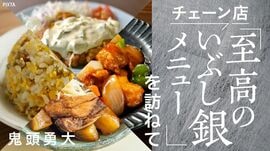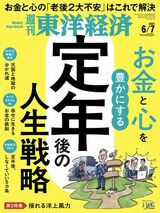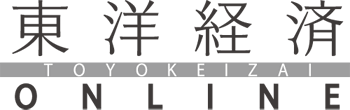「子どもがやる気を失う」危険すぎる"3つの行動" 親の声かけの仕方は大きく「2タイプ」に分かれる
……これを、毎朝やっているのです。これらは共感型でしょうか? それとも強制型でしょうか?
言うまでもありません。「指示」「命令」「禁止」の強制型です。
ちなみに共感型の親は、「靴下履いたほうがいいと思わない?」と考える余地を持たせるのだとか。そうすべきなのはわかっていても、日々の生活のなかでついつい強制型になってしまうのです。
子どもの非認知能力を育てていますか?
共感型のアプローチが、なぜ子どもの学力に影響するのか。それには深いワケがあるそうです。
また別の実験ですが、マシュマロテストというのを聞いたことはありませんか? 非常に有名なテストで、次のようなものです。
マシュマロが好きな子供の目の前にマシュマロを1つ置き、「このマシュマロを食べずに我慢できたら、あとでマシュマロを2つあげるから我慢できる?」と質問します。「我慢できる」と約束した子どもが本当に我慢できるか、我慢できずに目の前のマシュマロを食べてしまうかで、その後の発達に影響があるか調べたテストです。
なお、マシュマロを食べずに我慢ができるかどうかといった能力を、非認知能力といいます。国語とか算数とか学力で測れるものを認知能力、それ以外の、意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケーション能力といった、学力では測定できない個人の特性による能力のことを非認知能力というのです。
なんと、この非認知能力の高さが、学歴、雇用、収入に影響することが明らかになっているそうです。
非認知能力の要素として先ほど紹介した、意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケーション能力、これって社会に出たら必要なものばかりですよね。
想像してみてください。