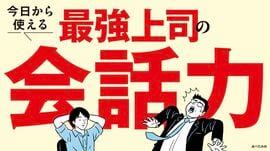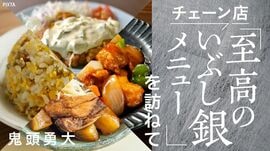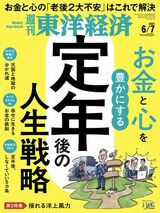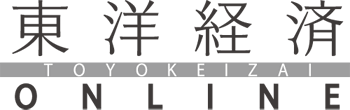「子どもがやる気を失う」危険すぎる"3つの行動" 親の声かけの仕方は大きく「2タイプ」に分かれる
強制型の親は、子どもに対して「指示」「命令」「禁止」をします。具体的には「これはこうしなさい」「これをやってみて」「これはやっちゃだめ」という声かけです。子どもに考える余地を与えず、たとえば「ママはそう言ったかな? 違うでしょ」というふうにして、子どもをコントロールするのです。
一方、共感型の親は、子どもに対して、「褒める」「励ます」「広げる」をします。「すごいね」「できるよ」「どうしてそうしたのかな? 面白いね」「こうしてみたらどう?」といったような声かけです。子どもに考える余地を与え、自分で選ばせるというアプローチ方法です。
この2つの声かけによって、子どもの将来の学力にどういう影響があったのか。
なんと、共感型で育てられた子どもにはその後の学力に飛躍的な上昇が見られ、強制型の子どもよりも成績がよく、司法試験などの難解な試験の合格率も高かったそうです。
ついついやってしまう、「指示」「命令」「禁止」
この実験結果を踏まえて、日ごろの自分の子どもに対してのコミュニケーションが、強制型なのか共感型なのか、改めて考えてみましょう。
自分は共感型として接していると思いたくなるのですが、日常のやりとりは、つい強制型に陥りがちです。
たとえば、我が家の保育園に行くまでの準備。
うちの子は本当にのんびり屋で、起きて、トイレに行き、ご飯を食べ、歯を磨き、着替えて靴下を履いて靴を履き、家を出る、という朝のルーティンを、毎日毎日ちんたらちんたらやるのです。
私は出張も多く、時間が不規則なので、我が家で息子を起こすのはもっぱら妻の役割になっていました。普段冷静で、優しく対応する妻も、毎朝やられると、たまったものではないようで、最初のうちは「時間だよ、起きな~」「朝ですよ~」とマイルドに始まるのですが、時間も迫ってくると、だんだんと語気が荒くなり、
「早くご飯食べて!」
「歯磨きして、間に合わないよ!」
「着替え!! 違う!! 前後ろ逆!!」
「靴下!!」
「はい、靴履いて。あと5秒!! 5、4、3、2、1、時間切れ!!」
「遅れてもいいの? 知らないよ?」
「いいかげん自分でやって」