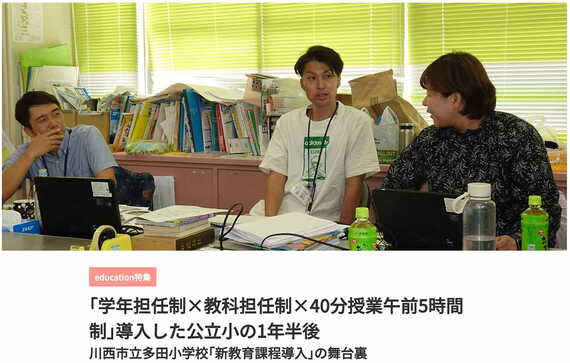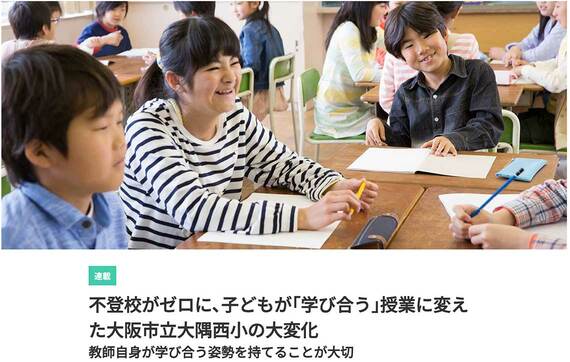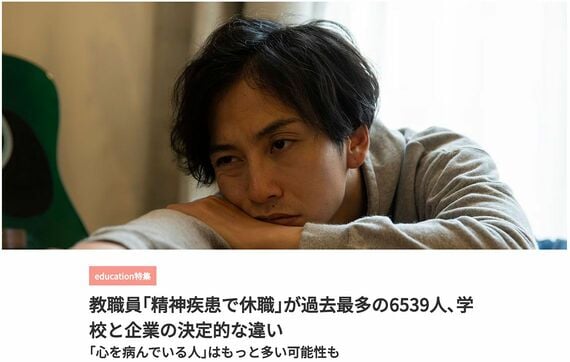教員の給料アップでも「業務削減」必須の訳、学校現場「働き方改革」に高い関心 教育関係者へ「2024年に読まれた記事」トップ10

川西市立多田小学校の新教育課程の成果
川西市立多田小学校(兵庫県川西市)では、2023年度より「学年担任制」「教科担任制」「40分授業午前5時間制」を組み合わせた新教育課程を導入した。この取り組みは、教員の負担を軽減して多様な働き方に対応するとともに、児童の自律を促すことを目的としている。
導入から1年半を経て、どのような成果や課題が見えてきたのだろうか。校長の西門隆博氏と、新教育課程のプロジェクトリーダーを務める森優太氏に聞いた。
「学年担任制×教科担任制×40分授業午前5時間制」導入した公立小の1年半後
精神疾患による休職者に寄り添う「ゆきこ先生」
文部科学省が2023年12月に公表した「令和4年度公立学校教職員の人事行政状況調査」によると、教職員の精神疾患による休職者数は6539人で過去最多となった。休職には至っていないものの、疲れ切っている教員も少なくないだろう。
今、そうした教員たちに寄り添うのが、「ゆきこ先生」こと渡邊友紀子氏だ。適応障害で休職した経験を基に、SNSを通じて教員の相談に乗っている。渡邊氏自身は休職を機に、働き方をどのように見つめ直し、現場に復帰したのだろうか。
「ある朝学校に行けなくなった」適応障害で休職した教員が復職後に手放したこと
大阪市立大隅西小学校に起きた大変化
「今から20年前、子どもが主体的に学ぶ授業を目撃し、目から鱗の衝撃を受けた」ーー。
そのときから試行錯誤で子どもたちに任せる授業スタイルを完成させていったという大阪市立大隅西小学校校長の原雅史氏は、2017年に小学校の校長になったことをきっかけに学校全体で学び合いの授業に取り組んできた。
どんな授業なのか、子どもたちはどのように変わったのか。教育ジャーナリストの中曽根陽子氏が取材した。
不登校がゼロに、子どもが「学び合う」授業に変えた大阪市立大隅西小の大変化
精神疾患による休職者対応、学校と企業の違い
ここ数年、年間5000人台で推移していた教職員の精神疾患による休職者数が、ついに6000人を超えた。
学校現場の休職者数が高止まりしたまま、なかなか改善に至らないのはなぜなのか。そして教職員のメンタル対策には何が必要なのか。企業向けのメンタルヘルス対策支援で成長し、教職員向けの支援もスタートさせたメンタルヘルステクノロジーズ社長の刀禰真之介氏に話を聞いた。
教職員「精神疾患で休職」が過去最多の6539人、学校と企業の決定的な違い
「昭和すぎる学校」4つの損
お便りや配布物は紙、集金は現金、問い合わせは電話が中心など、いまだ学校では多くの業務がアナログで行われている。小中学校の児童生徒1人に1台の端末を整備するGIGAスクール構想とあわせて、校務においてもDXが進められているが、その歩みは遅いといわざるをえない。