すき家の「ディストピア飯化」が密かに物議のワケ おっさん客がネットで激怒?も全然笑えない理由
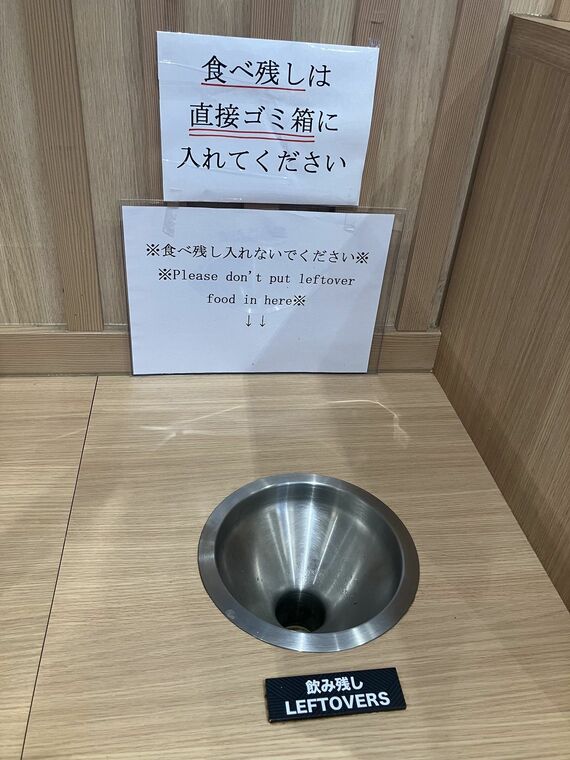
とにかく、容器が変わったことによって「店内で食べる温かみがなくなった」とか「おいしさが半減」という投稿が目立つのだ。また、深く読み解くと「もてなされている感覚がなくなった」と訴えているように見える。
ここで私が難しいと思うのは、顧客側にとって望ましくないと感じられる施策でも、店側にとっては、作業量が大幅に減り、間違いなく現場の負担軽減に役立っていることである。
賃金アップをするにも限界がある現在、食事の「温かみ」や、外食しているという「特別感」を演出することと、従業員の働き方のバランスを取ることはとても難しい。
そもそも、アルバイトであることも多い店員に「温かみ」を求める私たちのほうが横暴なのかも…?とも思えてくる。
「温かみがない」と批判され続けてきたファストフード
さて、この点を考えるとき、ファストフードの歴史にさかのぼってみると、新しい視点を持つことができる。というのも、そもそもファストフードは、「温かみがない」と批判され続けてきた歴史があるからだ。
牛丼チェーンをはじめとするファストフードがここまで私たちの生活に広く浸透するようになったのは、1970年代ぐらいから。ファミリーレストランの草分け的存在である「すかいらーく」が1970年に誕生し、マクドナルドの1号店は1971年に誕生している。
牛丼チェーンも似たような時期に生まれていて、吉野家がチェーン展開を始めたのは1968年、松屋の1号店が始まったのも1968年だ。すき家は少し遅れて1982年に創業しているが、とにかく1970年代を境に、どんどんとファストフードが増えていった。
ファストフードの大きな特徴は、各店舗に食べ物を配送する「セントラルキッチン方式」を導入したことにある。これは、中心となるキッチン(セントラルキッチン)で食べ物を作って各店舗に配送して店で提供する仕組み。店舗運営の合理化を目指すチェーンストア方式には持ってこいのやり方であった。牛丼家もこうした方式を取り入れている。
ただ、このようにセントラルキッチン方式が増え、郊外を中心にチェーンストアがあふれ始めると、こうした合理的なシステムに生活が覆われていくことに対して、批判的な論調も現れてくる。
そうした批判的な意見の中には、「人と人とのコミュニケーションをこうしたチェーンストアが失わせた」なんてものもあって、まさに、今回のプラ問題で顔を出した「食事の温かみ」問題に触れるようなものもある。
例えばこの点に関してもっとも手厳しい批判をしたのが、評論家・三浦展かもしれない。彼は『ファスト風土化する日本』の中で、食材の生産者と作り手の顔が見えない、ファストフードのシステムが日本人の生活スタイルを荒廃させていて、もう一度顔が見える関係の中での食事や生活スタイルを取り戻すべきだと述べている。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら