みずほ信託、「ひとり親」を救うファンドの正体 社会貢献と会社利益の「二兎」を追えるか
行政やNPO法人などが生活支援サービスを提供する一方、「金融の力」でひとり親家庭を支援する取り組みを進めるみずほ信託。だが、金融商品として収益性を確立させることは一筋縄ではいかない。
その象徴が家賃設定だ。高い家賃を支払えないひとり親家庭と、高いリターンを求める投資家との目線のすり合わせは容易ではなく、現在も商品設計の模索が続いている。
2021年に厚生労働省が実施した調査によれば、ひとり親家庭の平均収入は父子家庭で518万円、母子家庭で272万円。家賃の支払いは年収の3分の1程度が望ましいとされ、そこから弾いた後者の家賃負担能力は、手取りベースなら月5万~6万円程度となる。
ファンドを企画したみずほ信託銀行・不動産コンサルティング部の設楽彰憲班長は、「家賃相場が月15万円程度の2~3LDK住戸なら、5万円ほどで貸し出したい」とする。
通常のファンドに比べて利回りは落ちる
一方、安い家賃で貸し出せば投資家のリターンが減るうえ、マンションの管理や修繕費を賄いにくい。そこで、ひとり親家庭向けの住戸は全体の2割程度にとどめ、残りは相場並みの賃料で一般家庭に貸し出す計画だ。

家賃の引き下げがリターンに与える影響を薄めるだけでなく、ひとり親家庭向けと一般家庭向けの住戸を混在させることで、対外的に誰が低所得者層かをわかりにくくする効果もある。
表面利回りが4%で流通している1棟マンションにおいて、2割の住戸を3分の1の家賃で貸し出した場合、単純計算で利回りは約3.3%に落ちる。1%弱の下落は社会貢献の対価として、投資家に理解を求める。
「通常のファンドと比べて利回りは落ちるが、社会貢献に資することを投資家にアピールしたい」と、設楽氏は強調する。
ファンドの組成と並行して、NPO法人と連携したひとり親家庭の募集や入居者の自立支援も検討する。





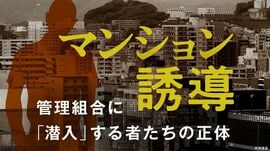









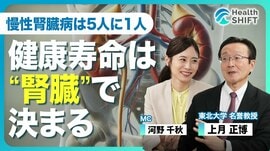
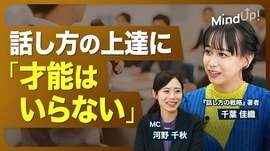





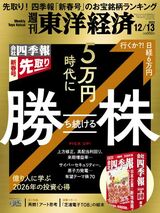









無料会員登録はこちら
ログインはこちら