住宅市場の低迷は、長期にわたり中国経済の足を引っ張る可能性が高い。

中国では、2021年夏に表面化した恒大集団(以下、恒大)をはじめとする不動産開発企業の債務問題をきっかけに住宅バブルがはじけた。
これに対して、政府が不動産開発企業の債務再編と資金調達への支援や、住宅ローンの融資条件の緩和を中心に対策を講じている。
しかしキャピタルゲインを狙った投機的資金が住宅市場から引き揚げられることや、住宅の一次購入者となる年齢層(30〜34歳)の人口が減少に転じていることなどから、住宅市場の低迷が長引く可能性が高い。
多くの不動産関連企業や住宅の所有者、銀行などは、資産が目減りしており、バランスシート調整を余儀なくされている。その結果、マクロ的には投資と消費が伸びず、コロナ後の景気回復は遅れている。
恒大から債務危機広がる
中国では不動産開発企業は経済成長や都市化の波に乗って、借金に頼った住宅建設を進め、高い利益を得ていた。その一方で、住宅を対象とする投機も盛んになり、住宅価格はバブルの域に達した。

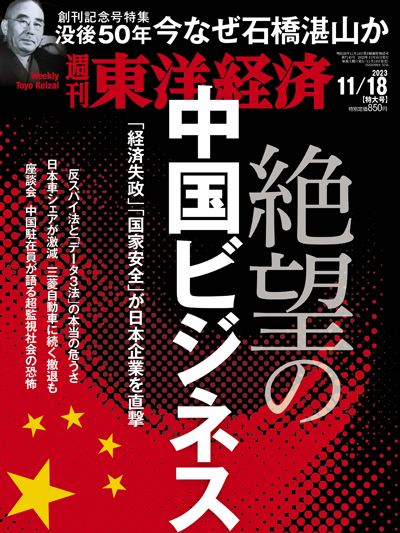
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら