初心者に頻発「センスなし資料」を避ける4つのコツ センスあり資料となし資料の違いを紐解くと…
③長さが中途半端
図形内の余白は十分にとられているものの、図形自体の長さが中途半端で窮屈な印象があり、浮いているように見えてしまいます。左上の図形のように、背景写真の端いっぱいまで長さを伸ばすことで、違和感が解消されます。
④境界線がある
図形や文字に境界線をつけると、要素を強調して視認性を上げることができます。しかし、場合によってはごちゃごちゃとした初心者っぽいデザインに見えることも。
今回の場合、白い図形を置くだけで十分に文字を読みやすくできているので、境界線は不要です。あえてポップなデザインにしたいなら境界線を使うのもアリですが、それ以外は使わないほうが無難であると言えるでしょう。
①〜④をすべて修正すると、次のようなデザインが出来上がります。

最初の画像と見比べると、どちらが見やすく、情報が伝わりやすいかは一目瞭然です。自分の資料を見て違和感を覚えたときは、その理由を言語化して修正してみてください。
伝わりやすい資料を作るためのチェックリスト
図形デザインで押さえるべきポイントとして、①文字を読みやすくするときは図形を100%表示にする、②図形内に余白を作る、③中途半端な長さにしない、④境界線はつけない、の4つをご紹介しました。
ほかにも次のような要素を押さえておくと、「センスいいね!」と言われる、情報が伝わりやすい資料を作ることが可能です。「この資料、なんだか微妙だな」と感じたら、チェックリストを振り返ることをおすすめします。
・フォントは明朝体やポップ体ではなく、ゴシック体を使う
・文字サイズは優先順位に沿って変える(重要な箇所を大きくする)
・色を多用せず、意味のある色分けにする
・矢印や強調線など装飾系の図形は小さくする
・図形は塗り+線にせず、塗りだけor線だけにする
・丸を使う時は楕円ではなく正円にする
上記は必ずしも守らなければならないルール、というわけではありません。資料によってそのデザインにすべき理由があれば、柔軟に対応しても構いません。
資料作りをはじめとしたデザイン制作において大切なのは、デザインの背景にある意図を言語化できるようにすること。先ほどもお伝えしたように、身の回りの風景に隠れている1つひとつの要素に注目して「何がどのようになっているか?」を見ること、次に「なぜそうなっているのか?」を深掘りして考えることで、デザインスキルは向上していきます。
1つのデザインから複数のテクニックを発見し、自分の中に蓄積していけば、チェックリストなしでもセンスのある資料を作れるようになっていくはずです。資料作りはもちろん、後輩や部下から上がってきた資料を添削するとき、面白い企画を発見したとき、ひいては仕事以外のシーン(パートナーが怒ったときなど)にも応用できるようになります。
資料作りのセンスは仕事の中だけでなく何気ない日常においても鍛えられるもの、そして資料作り以外の場面でも活かすことができるものだと言えそうです。辺りを見渡すと目に入ってくる数々の視覚情報から出来るだけ多くの「なぜ?」を膨らませて、今すぐ実践の場に役立てていきましょう。(編集協力:榎谷ゆきの)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

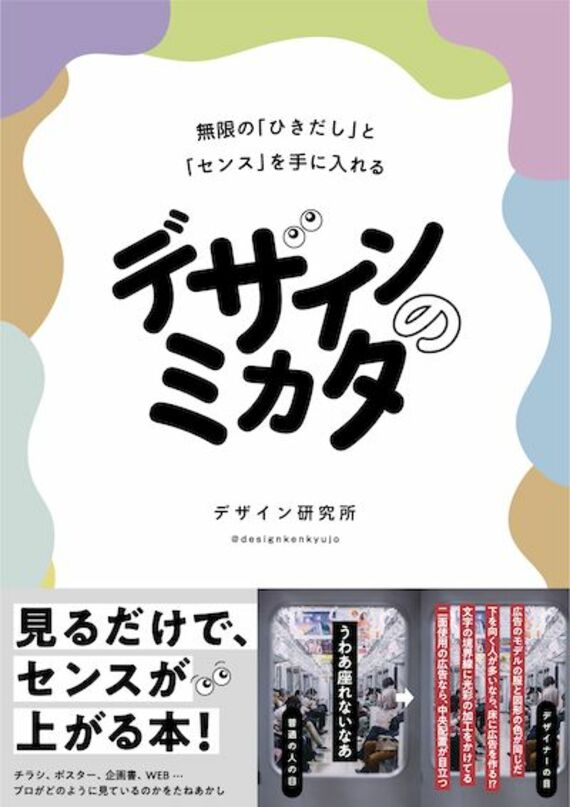






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら