子どもが伸びる中高一貫校はどこか? 話題の学校の中から東京農業大学第一中学・高校の取り組みを紹介する。

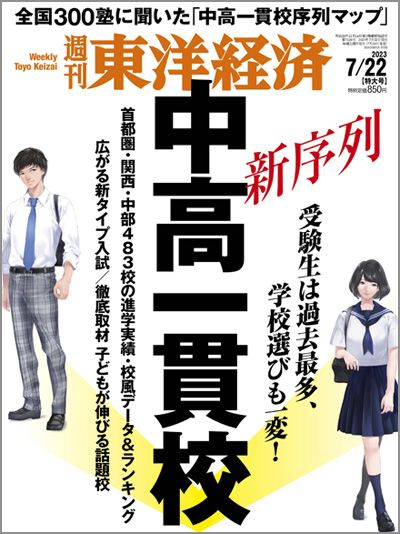
水溶液に入れた葉から出る気泡を生徒たちが観察する。東京農業大学第一中学・高校の中学1年生の理科の授業の一コマだ。生徒たちは、葉が入った容器と光源の距離を変え、光の強さと光合成速度の関係について学んだ。
同校は、本物に触れ学びを深める「知耕実学」を教育理念にする。とりわけ、併設する東京農業大の実験設備を使った実習が特色だ。
中1の総合学習で取り組む稲作は、コメが育ちやすい土壌や気候について学び、田植えから収穫までを体験する。今年はコロナ禍の影響で別の場所だが、通常は同大の厚木キャンパスで行う。中2では収穫したコメの食べ比べも行う。東京農大の教授の指導の下、電子顕微鏡を使い、新米と古米の色や形、風味の違いを知る。



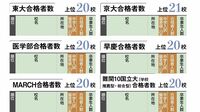





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら