異次元緩和には「前史」がある。四半世紀に及ぶその秘史をひもとく。
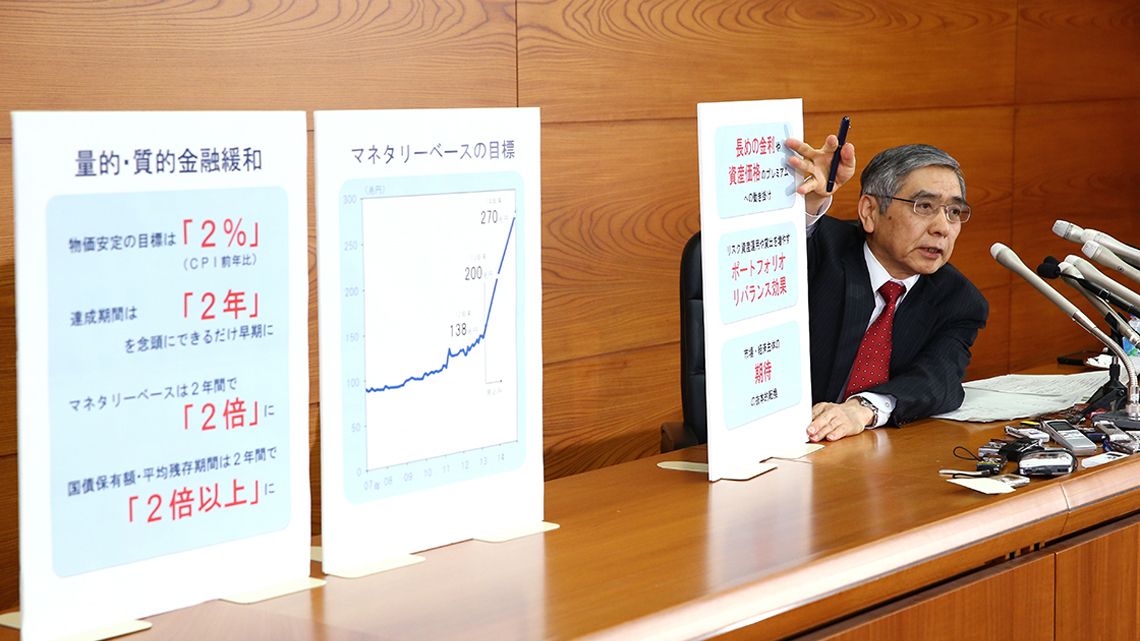
開始から間もなく10年になる異次元緩和には、さらに17年に及ぶ「前史」がある。
バブル崩壊後の潜在成長力低下としぶといデフレ圧力の下、日銀は懸命に知恵を絞り、時には政治圧力に抗しながらも、「防衛ライン」をじりじりと下げ、後ずさりを続けた。それは第2次世界大戦末期に退却戦を強いられた日本軍を見るようでもある。四半世紀に及ぶ日銀のデフレとの闘いを回顧する。
きっかけは雨宮ペーパー
振り返れば、日銀が「ゼロ金利後の世界」を気にし始めたのは、今から28年前、1995年の春ごろだったと記憶する。メキシコ通貨危機を発端に円相場が急騰し、3月に1ドル=90円割れの「スーパー円高」が到来したのだ。
当時の中心的な政策手段の公定歩合は、史上最低の年1.75%。これ以上の引き下げは避けたいと考えた日銀中枢は、FRB(米連邦準備制度理事会)の手法に倣い、公定歩合ではなく、短期金融市場の操作対象である無担保コールレートの水準変更を公表するスタイルに切り替えようと画策する。
公定歩合を温存しつつ、一方でアナウンスメント効果を確保しようというのが狙いで、「コールレートの低め誘導とその対外公表により1、2カ月ほど様子を見る」という基本戦略が固まった。
だが、3月末に発表した低め誘導は、逆に公定歩合引き下げに消極的だと受け止められ、株価の急落と一層の円高を招く結果となる。結局、大蔵省の強い説得により、4月14日、公定歩合を0.75%分引き下げざるをえなくなった。その半年後、公定歩合はさらに0.5%分下がり、「ゼロ金利」がはっきりと視界に入ってきた。
日銀中枢で「ゼロ金利後」が議論され始めたのは、まさにそんな退却戦のさなかだった。当時、企画課調査役だった雨宮正佳(現副総裁)は、後に採用される日銀当座預金のコントロールに関するペーパーを書き、上司に提出した。企画局長はこの「量的緩和案」に興味を持ち、役員集会に報告したという。
雨宮はまた、当時タブー視されていた長期国債の買い増しについても「買ってみなければ効果があるかないかわからないじゃないですか」と、何度も議論を挑んだ。




































無料会員登録はこちら
ログインはこちら