東大と京大、数学入試に見た「求める学生」の違い 総合力の東大、未熟でも自己表現を求める京大
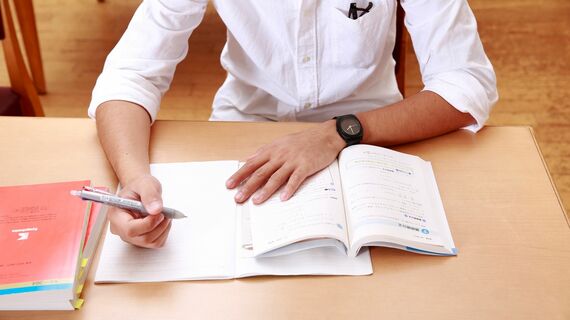
東京大学の求める学生像
東京大学のアドミッション・ポリシーの中には、「高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと」という項目があります。この中で数学については以下のように書かれています。
目の前の問題から見かけ上の枝葉を取っ払って数理としての本質を抽出する力、数学的な読解力が求められています。
自分の考えた道筋を他者が明確に理解できるように「数学的に表現する力」を重要視します。解答を導くだけでなく、解答に至る道筋を論理的かつ簡潔に表現する訓練を十分に積んでください。
数学を「言葉」や「道具」として自在に活用できることが要求されますが、同時に、幅広い分野の知識や技術を複合して「総合的に問題を捉える力」が不可欠です。
こういったことを踏まえて東京大学の数学の試験問題を見てみましょう。
東京大学の数学の特徴は、以下の4点だと思います。
実際に、1999年第1問の加法定理の証明や、2003年理系第6問の円周率の近似問題など、今までとは大きく傾向を変えた問題を「実験的に」出題する傾向があります。その出題の後、例えば2013年大阪大学理系第1問の極限公式の証明のように、東京大学に追随して類似問題を出す大学も出てきます。このように東京大学は日本の大学を牽引する立場、ひいては「世界の東京大学」としてあるべく、入試を捉えているように思います。



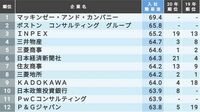



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら