工業生産力モデルで外貨を稼ぐ日本の産業構造は、どこで劣後したのか。挽回策は。

日本のものづくりは解体の危機
雇用を創出し、外貨を稼ぎ、日本経済を支えてきた日本の製造業。基幹産業が細っていく事態にどう対応すべきか。寺島実郎・日本総合研究所会長に聞いた。

──世界の中で日本の産業競争力が埋没しています。
戦後の日本は、米国にコバンザメのように張り付いた工業生産力モデルで一定の成功を収めた。だが、その前提となっていた産業資本主義が冷戦の終焉でパラダイム転換を起こした。
具体的には、軍事技術から生まれたインターネットを基盤とするデジタル資本主義が1つ。もう1つが金融資本主義だ。米国の軍事産業を支えた理工系人材が生み出した金融工学がベースとなった。
その2つは連携し、ITベンチャーが株式公開やM&Aといった形で肥大化していく。その代表格がGAFAM(ビッグテック)だ。日本ではGAFAMは生まれなかった。こうしたパラダイム転換に日本の工業生産力モデルがついていけなかった。
──日本の製造業はなぜ劣後したのでしょうか。












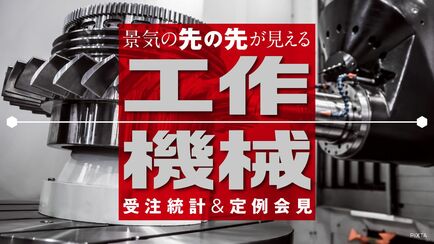






















無料会員登録はこちら
ログインはこちら