グローバル展開に成長機会を求めつつ、国内の生産基盤の維持にもこだわる。そんなトヨタ自動車のあり方から、日本企業が学ぶべきものは何か。ものづくり経営論の大家である藤本隆宏氏に聞いた。

──日本の製造業の競争力をどう評価していますか。
産業と企業と現場で評価は違う。産業は自動車などすり合わせ型が好調、テレビなどモジュラー型が不調だ。設計の比較優位の見極めが重要だ。産業に浮沈はつきものだが、テレビがダメなら全部ダメという悲観論は経済学的な根拠のない俗論だ。
企業の本社経営も玉石混淆の様相だ。現場や技術の強さを生かし切れない本社もまだ多い。おおむね、潮目を読み切る社長がいる会社は元気、空気を読む社長のところはダメな傾向がある。
そうした中、貿易財のよい現場は過去二十数年の逆境に対しあきらめず能力構築し、中国拠点の2倍から5倍の生産性も珍しくない。賃金差が5倍を切ればコスト競争力が復活する。あきらめず能力構築する現場は生き残る確率が高まった。「グローバル能力構築競争」の時代が来つつある。

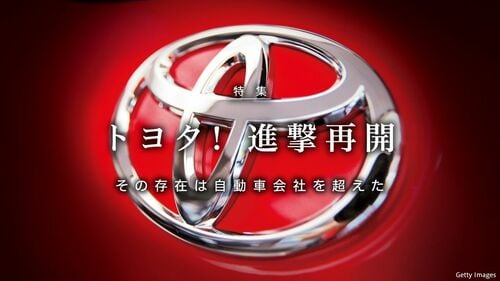































無料会員登録はこちら
ログインはこちら