
1度診察に出ると、朝まで1都3県をひたすら車で走り続けることになる。移動中にも次々と訪問要請が入り、息をつく暇もない。
「ERドクターやスタッフたちの負担が極限にまで達しているのは事実。でも今や救急車を呼んでも、重篤でない限り病院が受け入れてくれない現状があり、私たちのような業者がいなかったら、見捨てられる患者さんが今以上にあふれてしまう」(菊地氏)
公的な救急車だけでは多くの患者が見捨てられてしまう。だから、走り続けるしかない。夜の街をひたすら駆け抜ける、〝流しの救急隊〟の日々は過酷そのものだ。
熾烈を極める訪問診療の現場
9月初旬、筆者は専用車両に同乗させてもらい、医師の話を聞いた。夜21時過ぎ、事務局からドライバーのスマホに連絡が入る。「荒川区、28歳、男性。38度の発熱あり。PCR検査と診察の要請。至急、向かってください」。

要請を受け、医師と看護師は現場に急行。車内で防護服に着替え、患者宅に入っていった。診察を終え、車内に戻った医師は汗だくだ。
「防護服がめちゃくちゃ暑い。これ着るのが嫌だからコロナ患者はごめんだっていう医師が多いのもわかる」
日頃は勤務医として都内の総合病院で働く男性医師はそう言うと、ペットボトルの水をがぶがぶと飲み干した。患者はどうだったのか。「若いサラリーマンの方で、コーヒーの味が明らかに変だと言っていたので、コロナだろう。ワクチン未接種で、先週2回も友人と居酒屋で飲んだと言っていた。正直、こうした若い患者さんを診察するときは、こっちもびくびく。私にも小さい子供がいるので」。
この男性医師によると、コロナ第5波以降、明らかに20代、30代の若い年代の患者が増えており、かなり重い症状の人も多いという。
「デルタ株が流行し始めてから、明らかに様相が変わってきた。若い人でも『死ぬほどつらい』と訴える人が増え、実際、中等症以上の患者さんも増えている」
次に向かったのは、自宅療養中だという40代女性のコロナ患者の部屋。1週間前に陽性が判明、38度以上の熱が続き歩くのもつらいという。


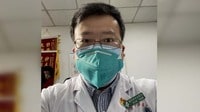




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら