アダム・スミスが経済学を語る上で外せない訳 「神の見えざる手」はしばしば誤解されている
『道徳感情論』は『国富論』の20年近く前に執筆されたスミスの処女作で、なぜ人々は法がない状態でも道徳的に振る舞い、社会は秩序を保っていられるのか、社会秩序を導く人間の本性とはなんなのかが、経験主義的に考察されています。
スミスは、神や聖書といった超越的ななにかに規範の源泉を求めるのではなく、人間の持つ「共感、同感」(fellow feeling, sympathy)というものを共通の出発点として、内面化された「公平な観察者」(impartial spectator)と いう立場から、物事の「適合性、適宜性」(propriety)を説明するという形で、人間そのものの中に、道徳や規範の根拠を求めようとしました。
理性ではなく道徳感情によって基礎づけられる秩序
スミスは、ホッブズが『リヴァイアサン』で述べている、人間の自然状態を、個人同士が互いに自然権を行使しあった結果としての「万人の万人に対する闘争」とする前提は誤っていると批判し、本書のタイトルに象徴されるように、社会秩序は理性ではなく道徳感情によって基礎づけられていると結論づけたのです。
また、スミスは、古代ギリシアのエピクロス派とストア派について、自らの考えと比較しながら論じています。
人生の目的は快楽であり、自然で必要な欲求(友情、健康、食事、衣服、住居などを求める欲求)だけを追求して、苦痛や恐怖のない生活を送ることが善であるとしたエピクロス派に対し、ストア派は、徳は自然と一致した意志にこそ存するとして、規則に従って生きることを通じた道徳的・倫理的幸福の追求を提唱しました。
スミスは、エピクロス派の体系については、自分がこれまで確立しようと努めてきた体系と両立しないと述べる一方で、ストア派については、「賢人」と「公平な観察者」を重ね合わせて、肯定的な見解を示しています。
スミスは『道徳感情論』を生涯に6回も書き直しており、1790年の最終版では、1776年に出した『国富論』がその構想の一部であった旨を序論につけ加えています。
現在では、『国富論』は、単なる自由放任と弱肉強食を説いた市場至上主義的な思想書ではなく、共感を持つという人間像を前提とした経済理論であるとして、両書をいわば「車の両輪」とした幅広い見地からの研究がなされています。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

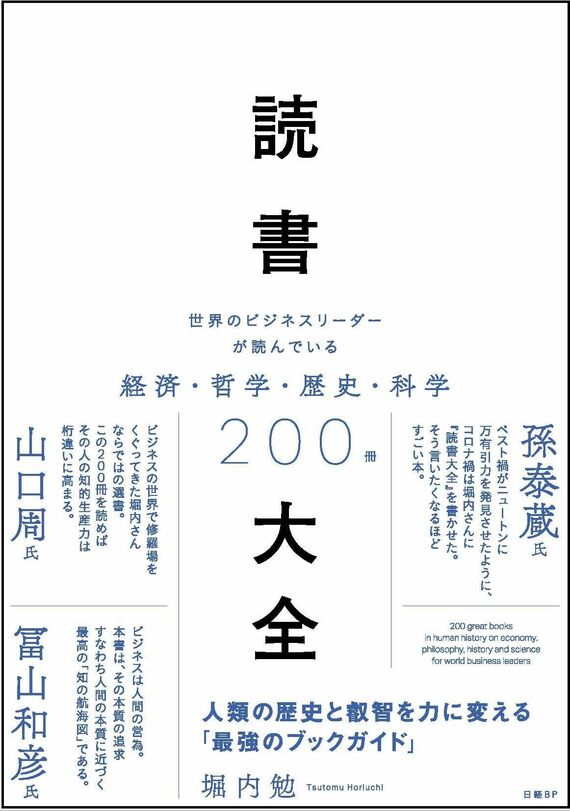






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら