世界の哲学者が考える「テレビ」に問われる役目 TVの鑑賞は哲学ではどう位置付けられているか
一時期、日本でもテレビは「1億総白痴化」するものとして、批判された時期がありましたが、その原型はここにあるのがわかります。テレビは文化産業に支配され、視聴者を画一化し、「白痴化」する、というのです。しかも、超小型のため映画のような迫力がなく、視聴者は玩具に対するように優越感に浸りながら、「見ざるをえない」という形で奴隷となってしまうのです。
しかし、こうしたテレビ理解は、今でも妥当なのでしょうか。アドルノのテレビ論が書かれてからおよそ50年以上たった頃、ドイツのハンス・マグヌス・エンツェンスベルガーは「TV・ゼロのメディア――テレビについてのあらゆる歎きはなぜ無効なのか」を書いて、「テレビ=白痴化」という意見を徹底的に批判しました。彼はその論文を、次のように始めています。
テレビを理解し直すことが必要
TVはひとを愚かにする、という素朴なテーゼに、普通のメディア理論のほとんどは帰着する。精密に見える理論であれ、お粗末な感じのものであれ、その点は変わりがない。そしてあの所見はたいてい、怨恨を底に秘めた調子で語られる(エンツェンスベルガー『ドイツはどこへ行く?』)。
エンツェンスベルガーによれば、こうしたメディア理論は4つに分類できます。①メディアにはイデオロギーの次元がある、と結論する操作理論。②メディアを受容し消費することは、何よりも倫理的危険をともなう、と見る模倣理論。③視聴者は現実と虚構とを区別する能力を、メディアによって奪われる、と考える新しいシミュレーション理論。
④メディアはその利用者の批判・識別能力や倫理的・政治的資質を蚕食するだけにとどまらず、彼の知覚能力をも、さらには精神のアイデンティティをさえも蚕食する、と見なす愚昧化理論。こうした4つの理論を挙げた後で、エンツェンスベルガーは「これらの理論はいずれも説得力に欠けている。理論の提起者たちは、証明なしで済ませている」と批判しました。
かなり手厳しいですが、決して的外れの非難ではないでしょう。しかも困ったことに、こうした理論は、今でも素朴に繰り返されることが多いのです。とすれば、テレビをどう理解するかは、あらためて問い直されなくてはなりません。
「白痴化」とか、「現実と虚構の混同」とか、「倫理的に有害」とか、「政治的利用」とか、――こうしたTVの特徴づけは、どこまで根拠があるのでしょうか。もしこれが根拠のないものだとすれば、テレビとはどんなメディアなのでしょうか。この問いは、今でもきちんと答えられるわけではありません。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

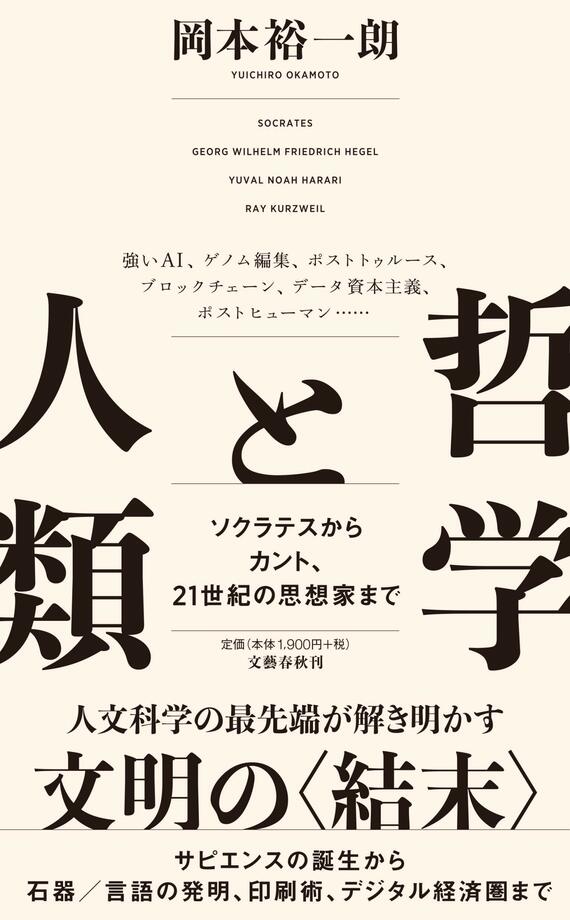































無料会員登録はこちら
ログインはこちら