
「エコロジスト」としてのマルクス像
──世界の環境保護運動の主役は、グレタ・トゥーンベリさんのような若者です。「資本論」といっても、若い人に響くのでしょうか。
本書が、ソ連さえ知らない若い世代にも広く読まれているのは、貧富の差が広がり、環境破壊も深刻化している中、「資本主義そのもののシステムの問題として考えるべきでは」と思う人々が増えているからでしょう。若い世代は、社会や環境が危機に陥っているという意識が強いので、「資本論」やエコロジーに取り組んだ晩期マルクスのエッセンスを紹介すると、強い関心を持ってくれます。
──マルクスが環境問題を研究していたという事実は、驚きです。
150年間眠っていた、マルクスの「研究ノート」などの新資料の編纂作業に私自身も関わる中、浮かび上がってきた新しいマルクス像がエコロジストとしての姿です。
マルクスは「新技術によって生産力を上げれば、危機は解決し、文明は繁栄する」という思想の持ち主だと一般に解釈されてきましたが、実際にはそうではなかった。私がその新資料の編纂作業に関わるようになったのは、福島第一原発事故の直後のことで、人間と自然の関わり方を真剣に考えたいと思ったからでした。




















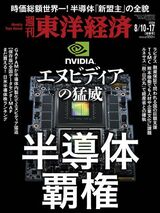









無料会員登録はこちら
ログインはこちら