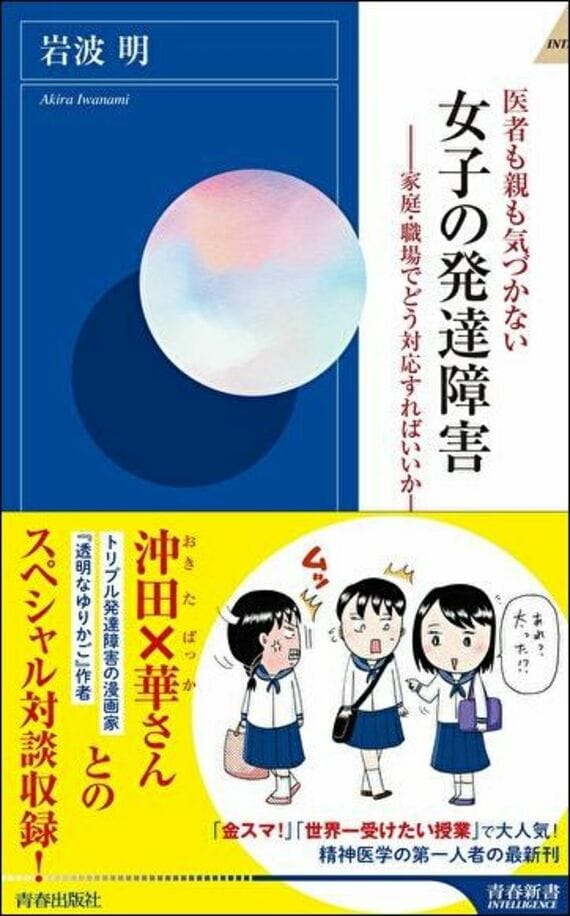発達障害「家族だけで解決するのが超危険」な訳 子供を「叱る」よりもまずは「離れる」を選ぼう
最終的には、本人が「これはまずい」と自覚して、自分から「変わろう」と思わない限り、本人の行動は変わりません。
親が援助する姿勢は大切ですが、同時に「家族が口で言っても、簡単には変わらない」ことは認識しなければいけません。家族にできないからこそ、病院などほかのアプローチが用意されている、と考えてください。
実はASDやADHDの治療をきちんとすることによって、さまざまな問題行動が少なくなっていくことは珍しくないのです。
治療をするうえで「いちばん避けたいこと」
そしていちばん避けたいのは、繰り返しになりますが、家族間の関係が悪くなることです。
病院で治療をするにしても、家族との関係が良好のほうが、問題の解決につながりやすいことは明らかです。口ゲンカばかりしていたら、治療の相談もできませんから。
父親と3人の子ども、合わせて4人が発達障害、というご家族の話です。息子さんふたりは、学力は十分なのですが、まったく勉強しないで家に引きこもりの状態。
とくに長男は父親に反抗的で、「俺が勉強できないのは、親父のせいだ!」と父親を非難してばかりいます。娘さんは、軽度の知的障害とASDを抱えています。
また、このお父さんがしょっちゅう子どもを説教するので、親子関係は険悪になる一方でした。実は父親にも、ASDとADHDの両方の特性がありました。「もう何も言わないようにしてください」と私から再三指示しているのですが、どうしても彼は小言を繰り返すことをやめられないようです。
父の職場での適応は治療によって改善しましたが、子どもたちの発達障害は、なかなか改善が見られないままでした。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら